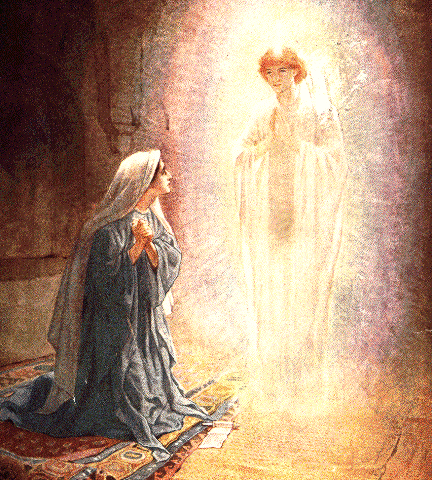臨死体験と聖書
「ニア・デス体験」とも「臨死体験」とも呼ばれる
体験は、聖書の教えとどう関わるのか

ボッシュ画のこの絵は、臨死体験者がよく証言する
トンネル(この世とあの世の境)のイメージを表している。
最近話題にのぼることの多くなったいわゆる「臨死体験」(near
death experience)と、死後の世界に関する聖書の記述との間に、矛盾や問題点はあるかということについて見てみましょう。
臨死体験とは?
最近では、救急医療や蘇生術(電気ショックや人工呼吸等)の発達により、一度死にながらも息を吹き返したという人々が少なくありません。彼らが、その"死んでいる間に"体験したこと・・それが「臨死体験」です。
臨死体験は、今日では非常に科学的な研究の対象になりました。多くの医師がこの研究に取り組んでおり、多くの書物が著されています。日本では、とくにNHKで立花隆氏をレポーターとする番組『臨死体験』が放映されて以来、それまで無関心だったような人々の関心も集めるようになりました。
臨死体験研究の先駆的なものとしては、レイモンド・A・ムーディ・Jr博士の著『かいまみた死後の世界』(評論社刊)があります。ムーディ博士は、バージニア大学病院の精神科医で、医学博士、また哲学博士という経歴を持っている人物です。
博士は臨死体験をした人々の例を一五〇ほど集め、統計的に処理しました。するとそこには、体験の内容に驚くほどの共通性があったのです。
そのほか、米国心臓学の専門家マイクル・B・セイボム著『「あの世」からの帰還』(日本教文社刊)、コネチカット大学教授ケネス・リング著『霊界探訪』(三笠書房)、ワシントン大学小児科学助教授メルヴィン・モースおよびアメリカン・ヘルス誌の元編集長ポール・ペリー博士の共著『臨死からの帰還』(徳間書店)、その他多くの研究が発表されていますが、いずれも臨死体験に共通するパターンについてすぐれた解説をしています。
彼らの研究結果や、そのほか日本人の研究者らの結果を総合してみると、臨死体験には、おもに次の要素が見られることがわかります。
(1) 死の宣告が自分に聞こえる
(2) 安らぎと満ち足りた感覚を味わう
(3) 肉体から離脱する(体外離脱)
(4) 暗いトンネルに入る
(5) 新しい世界が開ける
(6) 死者と出会う
(7) 光の生命体(光の天使)に会う
(8) 生涯を回顧させられる
(9) 生と死の境に立って、どちらに行くかの決定をする
ただし、臨死体験者の全員がこれらの要素を全部体験している、というわけではありません。全部体験した人もいますが、幾つかだけだった人もいます。それは臨死体験の深さによるのです。
臨死体験者の証言を幾つも集めて総合してみると、これらの要素が、死亡から蘇生の間に見られるのです。これらの要素について、一つ一つ詳しく見てみましょう。
(1) 死の宣告が自分に聞こえる
臨死体験者の多くは、自分が"死んだ"とき、周囲の人が死について語っていることを聞いた、と言っています。自動車事故で"死んだ"ある若い男性は、こう述べました。
「事故現場に居合わせたある女性が、『この人、死んじゃったの?』と尋ね、誰かが『うん、死んでるよ』と言っているのが聞こえました」(『かいまみた死後の世界』)。
また、ある男性はこう語っています。
「私は水辺でふざけていて落ち、頭を打ったんです。気がつくと、体を抜け出して空中に浮かんでいました。母がすっかり取り乱しているのが見えました。母は兄に向かって、あんたが押したから弟が落ちてしまったのよ、と叫んでいました」(『臨死からの帰還』)。
この種の証言は、あとで関係者から話を聞いてみると、たいてい事実と一致していることが確認されています。ある医者は、臨死状態にあった患者に蘇生術を施し、蘇生させることに成功した時のことについて、こう語っています。
「その場に居合わせた私は、患者の瞳孔が広がっているのを確認しました。しばらくの間、私たちは患者の蘇生に手を尽くしましたが、全然効果が現われないので、この患者は死亡したと判断しました。私は、一緒に手当をしていた医師に、
『もう一度やってみよう。それでだめならあきらめるしかない』
と言いました。その結果、今度は心臓が鼓動を始め、蘇生に成功しました。
あとでこの患者に、あなたが『死んだ』時のことで、何か記憶していることはないかと尋ねたところ、あまり多くのことは覚えていないが、先生が、
『もう一度やってみよう。それでだめならあきらめるしかない』
と言っているのを聞いたことだけは覚えています、と言ったのです」(『かいまみた死後の世界』)。
(2) 安らぎと満ち足りた感覚を味わう
臨死体験者の多くは、自分が"死んだ"直後に、肉体の苦痛が去り、安らぎと満ち足りた感覚を味わった、と証言しています。交通事故で"死亡した"主婦は、こう語っています。
「まるで、この世に私をつなぎ止めていた帯が切れたようでした。もう怖いとは思わなくなっていましたし、だいいち肉体の感覚もなくなっていました。周囲で働いている人たち(医師や看護婦)の声や物音は聞こえるんですが、どうでもいいことのように感じました」(『臨死からの帰還』)。
またベトナムで負傷し"死んだ"男性は、こう語っています。
「非常にほっとしました。痛みは全くありませんでしたし、あんなにゆったりした気分になったのは初めてでした。すっかりくつろいで、いい気分でした」(『かいまみた死後の世界』)。
(3) 肉体から離脱する
こうした感覚に加え、臨死体験者の証言の中で注目すべきことは、彼らが死と共に肉体から離脱したと証言していることです。
フィンランド政府の地域医療部長を務めるルーカネン・ギルデさんは、自分が手術を受けている時に、執刀医の医療ミスで臨死状態になり、体外離脱を経験しました。彼女自身、フィンランドでは高名な医者ですが、その時のことをこう証言しています。
「手術中のことでした。突然わたしは肉体を抜け出し、天井のあたりから手術の様子を見ていました。すると担当の医者が、メスを持ち上げ、静脈のかわりに、間違って動脈を切ろうとしていたのです。私はあわてて、
『そこは切っちゃダメ!』
と叫んだのですが、その医者には聞こえませんでした。彼はそのまま動脈を切ってしまい、血が天井まで吹きだしたんです。その後、私は『トンネル』を通り、光の世界に入りました。
手術後、目が覚めた私は、自分の見たことを担当医に話しました。でも彼は、『動脈を切った』とは言わず、「出血が多かったから幻覚を見たんだろう』と言いました。
そこで私は、医師の特権を利用して自分のカルテを見てみたんです。そこには、誤って動脈を切ったことが記されていました」(NHK『臨死体験』)。
ギルデ医師が、死んでいる間に自分の遺体から離脱して見ていたことは、このように事実だったのです。以来ギルデ医師は、魂の存在や死後の世界を信じるようになり、死への恐怖感がなくなったと言っています。そして臨死体験の研究者の一人になりました。
また、マイクル・B・セイボム博士は、臨死状態のときに体外離脱を経験したという人に、その体外離脱が幻覚か本当のものかを調べるために、次のようなインタビューを行ないました。患者は、五二歳で心臓発作を起こし心停止に至った人です。
セイボム「下を見おろされた時ですが、細かいことで何かごらんになったことはありますか。
患者「ええ、何でも見えましたよ。誰かの動脈が破裂してその血が壁に飛び散って、それを誰も拭き取らず、しみになったのとかですね」。
セイボム「ご自分の顔はごらんになれましたか」
患者「顔が横向きになっていたので、顔の右側や右耳が見えました」。
セイボム「(蘇生のために)電気ショックをかけられたときのことは、見えましたか」
患者「電圧が高すぎるように思いました。私の体が手術台から五、六〇センチも飛び上がったんですよ。そのあと、二回目にショックをかけられる前に、私は体に戻りました。
セイボム「その時自分のいた場所から、モニターをごらんになりましたか」。
患者「はい、オシロスコープみたいでした。薄い白い線が、ちょっと細かく振れている線が、下の方にさがってきました。細かく振れて見えましたけど、ほとんど直線のようになってたみたいです。心臓カテーテルをとった診察室のモニターみたいに大きいものじゃありませんでしたね。八インチくらいしかなかったんですよ。画面はいつまでも同じ線が出ていましたね。・・・・」(『「あの世」からの帰還』)。
インタビューはまだ続きますが、セイボム博士は、実際にその場にいた医師の協力を得て、この証言を検討、カルテの記載と非常によく一致していることが確認されました。また患者は、カルテに残されていない心臓への薬物の注入についても語っているのですが、それも事実と一致していました。
臨死体験者のほとんどは、こうした体外離脱について語っていますが、自分の遺体の周囲で起きたことを、自分の遺体とは別の位置から見ていて、あとで正確に言い当てたという例は、決して珍しいものではありません。むしろ、そのような例は枚挙にいとまがないのです。
ある人々は、こうした現象について「幽体離脱」という言葉を用いますが、「体外離脱」または「霊魂離脱」という言葉の方が、聖書的には適切でしょう。それは魂(霊)が、肉体から離脱する現象なのです(創世三五・一八、ルカ八・五五)。
体外離脱をした人は、自分の遺体より上方に浮遊して眺めることが多いようです。彼らはときに、天井に近い位置からでなければ見えないような事柄も語っています。
さらには、遺体の置かれていた病室のとなりの部屋で起きていたことを、あとで言い当てたという人もいます。二五歳のとき、出産後に不調を覚えて気を失って倒れ、そのまま"死亡した"女性はこう語りました。
「ベッド脇の床に倒れている自分の姿が見えました。細かいことまでよく覚えています。たとえば、私のガウンはウェストのあたりまでずり上がっていて、看護婦さんがそれを引き下げようとしていました。酸素吸入用の管がなかったので、オーダリ(病棟で働く男子職員)の方が酸素タンクを病室に引きずってきました。
看護婦さんが、『先生を呼んで、旦那さんに連絡して、牧師さんを呼んで』といったことを叫んでいるのが聞こえます。そのとき初めて、自分が体から抜け出していることに気がついたんです。
私はふわふわ漂いながらベッドに近づいていき、自分の姿を見おろしました。・・・・自分の体を見、濡れた髪の毛が枕に張りついているのも見ました。目は閉じていて、唇は青くなっています。でも私はそこにはいなかった。天井の近くまで浮き上がっていたんです。
耳が異常に鋭くなっていました。同じ階の患者さんたちの声が聞こえ、姿も見えました。廊下をはさんで向かいの病室に入っている患者さんが、私の病室の騒音のことで看護婦さんに苦情を言っています。
廊下の奥にある看護婦詰め所のデスクに、一人のお医者さんが近づいてゆくのが見えました。私が子どもの頃からお世話になっていた先生でした。看護婦さんが事情を話すと、先生は、
『彼女のお母さんには私から電話しよう』
とおっしゃいました。実際にそうしてくださっていたことが、あとでわかりました」(『臨死からの帰還』)。
体外離脱に関するこうした証言の多くは、みなこのように具体的であり、それが事実と一致していることもあとで確認されています。これは体外離脱がなにかの"幻覚"ではなく、現実のものであることを示しています。
とくに体外離脱者が、耳から得ることのできる情報以外のことも、多く語っていることは注目すべきことです。彼らは、実際に体外離脱して、遺体とは別の位置から見なければ知り得ないような事柄も、多く語っているのです。
(4) 暗いトンネルに入る
体外離脱のあと、臨死体験者の多くは、「暗いトンネル」を体験しています。落雷を受けて死んだ米国南部の自動車商は、こう語っています。
「嵐が来そうだというのに、ゴルフをしていたんです。そのとき、ものすごい衝撃を受けて、雷に打たれたんです。しばらく体の上に浮かんでいたのですが、やがてトンネルに吸い込まれてゆくのを感じました。
まわりの様子は何も見えなかったけれど、すごい速さで進んで行くのがわかりました。私は間違いなく、トンネルの中にいたんです。出口の光がどんどん大きくなってくるのが見えたので、わかったんですが」(『臨死からの帰還』)。
また、交通事故にあって臨死状態になった女性は、こう言っています。
「自分がトンネルの中にいるのに気がつきました・・同心円のトンネルです。あの体験をしてからまもなく、『タイムトンネル』というテレビ番組を見ました。らせん状のトンネルを通って、人間が過去の時代へさかのぼっていくのです。そうですね、思いつく限りでは『タイムトンネル』が一番似ています」(『かいまみた死後の世界』)。
(5) 新しい世界が開ける
光に満ちた澄みきった世界
トンネルを出ると、新しい世界が開けた、と多くの臨死体験者が語っています。心筋梗塞で"死んだ"ある男性は、こう語りました。
「私はそのトンネルを通り抜けたようでした。突然私は別の場所にいたのです。一面金色に輝いて、とてもきれいでした。どこから光がくるのかわかりませんでしたが、光はあらゆるところにありました。音楽も聞こえました。小川がせせらぎ、草や木や丘もある田園の中にいるようでした」(『続 かいまみた死後の世界』)。
また、九歳の時に高熱を出して臨死体験をした人は、こう語っています。
「私は、誰かに助けられてトンネルを昇って行きました。出口に着くと、目の前にきれいな風景が広がっていました。見渡す限り花いっぱいの野原で、右手にはきれいな道が延び、木々は根元から幹の中程まで白く塗られていました。
それから白い柵が見えました。何とも言えずきれいな眺めでした。右手を見ると、遠くに牧場があって、これまで見たこともないような見事な馬が何頭もいるんです」(『臨死からの帰還』)。
このように、トンネルを出て、美しい花園や田園、牧場、柵や木々を見たという人が非常に多くいます。

美しい花園を見たという人も多い
こうした美しい光景を見るか否かは、トンネルを抜け出るか、またはトンネルを抜け出る前に帰還するか、ということが境目になっているようです。
トンネルを抜け出る前に帰還した人々の中には、ときに不愉快、不安な感じがしたとか、気味の悪い思いをしたなどのマイナス・イメージを持った人がいます。しかしトンネルを抜け出るに至った人は、そこに美しい光景を見た、という人が非常に多いのです。
これは、トンネル以前はまだ"こちらの世界"であり、トンネルを抜け出ると"あちらの世界"に入る、ということなのでしょう。心臓疾患のために臨死体験をし、トンネルを抜け出た日本人女性も、全く同じ様な光景を見ています。
「果てしなく真っ暗なところを、上へ上へと昇っていくと、ぱっとまぶしいほど明るい世界へ飛び込んだのです。私は小高い丘に立っていました。じつに青々とした草原が広がっていました。
羊や馬がたくさんいます。背の低い潅木がところどころに立って、きれいな風景です。空もまぶしいほど明るく、気持ちのいい天気です」(新倉イワオ著『臨死体験』勁文社)。
こうした臨死体験者が見たという光景は、脳の側頭葉に刺激を与えるときに生じる幻覚に似ている、と言う人々がいます。しかし、セイボム博士によれば、臨死体験中に見聞する要素と、側頭葉の刺激による幻覚とは必ずしも一致しません。
とくに、先にみたように体外離脱において臨死体験者が見たと証言していることは、それが事実と一致しており、幻覚ではないことを示しています。
また、のちに見るように臨死体験者の多くは慈愛に満ちた「光の生命体」に出会ったと証言しているのですが、側頭葉の刺激による幻覚ではそのようなことは起きません。「光の生命体」は、臨死体験者だけが体験しているのです。
ですから、臨死体験者が見たという「花園」や「牧場」なども、同様に幻覚ではないでしょう。実際彼らはこうした光景を、肉体的には脳波停止、心臓停止、また瞳孔・肛門ともに開いた完全な死亡状態で見ているのです。
臨死体験者の中には、花園や牧場の先に川や湖を見た、という人も多くいます。ある老人は、自分が死亡状態にあったときのことを、次のように回想しました。
「すごくきれいなところにいたんですが、どう言ったらいいのか・・・・実際にあったのですが、想像がつかないでしょうね。川があるんです。聖書にも「川が流れています」(黙示二二・二)とあるでしょう。ガラスのようになめらかな川面で、そこを渡りました」(『続 かいまみた死後の世界』)。
日本人の中にも、川を見たという人が多くいます。ただ日本人の場合は、仏教の観念が強いからでしょうか・・これを「三途の川」と解釈している人が少なくありません。
しかし、臨死体験者の見た「川」と仏教の「三途の川」の間には、重要な違いがあります。「三途の川」では、鬼が出てきて、死者の服を脱がせることになっています。しかし臨死体験者の証言においては、日本でも外国でも、鬼に出会ったとか、服を脱がされたとかいう報告は全くありません。
さらに、こうした広々とした土地の向こうに、「建物」「町」「光の都」を見たという人もいます。臨死体験をしたある女性は、こう語っています。
「遠くに町が見えました。そこには建物は一つずつ離れて建っていて、明るく輝いているのです。人々は幸福で、泡立つ水や噴水があって、光の都とでも呼びたいような、素晴らしい光景でした。
美しい音楽も流れ、あらゆるものが輝いて・・・・美しく、もし私がこの町に足を踏み入れていたら、決して帰ってこなかっただろうと思います。そう言われたのです。・・・・私の決心次第でした」(『続 かいまみた死後の世界』)。
おそらく、この「光の都」が天国の中心部ということなのでしょう。それは聖書でいう「天のエルサレム」(ヘブ一二・二二)に違いありません。そしてその周辺の広々とした花園や牧場は、天国の周辺部なのでしょう。手術中に"死んだ"五二歳になる日本人会社員もこう語りました。
「暗いところを通り抜けたと思ったら、大きな宮殿みたいな建物があったな。ああいう美しい建物は、この世にはないですね。ぼくはそこへ歩いて行った。バラが咲き乱れたような道で、いい気持ちでした。だけど、そこへ行く前に目が覚めてね(蘇生)。まわりで家族が覗きこんでいた」。
空虚な空間や霧を見たという人もいる
しかし一方では、このように澄み渡った美しい世界ではなく、索漠とした空虚な場所や、霧の中にいた、と証言する人もいます。結核性の高熱で、ひきつけを起こして"死んだ"ある日本人男性はこう語りました。
「"ここはどこだ? どっかすごく遠い所へ来たな"って感じでした。あたりはすごく荒れ果てたような感じのところで・・・・だあれもいないんですね。ぼくはそこに・・立っていたのか浮かんでいたのか・・ともかく、いた。そしてぼくの前には、大きな川があった。・・・・色のない、すごい川でした。
しかも、川には橋がかかっていた。大きな木の橋みたいでしたが、これはそう思っただけで、さわって見たわけじゃないからわからない・・・・。しかし、なにしろ、はっきり橋と川だと感じた。
で、向こう岸には・・ぼくはジッと見てたつもりですが・・なんにもなかった。真っ暗いような感じでしたが、夜の景色というんでもない・・・・まあ虚無とでもいったらいいか、ものすごい空虚なところが、ずっと広がっていた」。
これに似た例として、空虚な「霧」の中にいた、という人もいます。子どものころ電線にふれて"死んだ"アメリカ人男性はこう語りました。
「トンネルの出口に着くと、そこにはぼやっとした白い霧がかかっているみたいで、何にも見えなかった。けど、それは光じゃなかった。雲か霧みたいで、でも明るかったですよ」(『臨死からの帰還』)。
しかし、さらに霧の向こうまで行くと、光の世界があった、と証言する人もいます。
「霧に近づくにつれて、霧の奥を見通せるようになりました。霧の向こうに、いろいろな人の姿が見えました。この世の人と完全に同じ姿形をしていました。建物のようなものも見えました。あらゆるものが目もくらむほどきらびやかな光に包まれていました」(『かいまみた死後の世界』)。
これらの証言から判断する限り、澄みきった広い場所・・花園や牧場と、霧の場所とは、隣り合わせに存在しているようです。澄みきった広い場所は天国の周辺部であり、その辺境部に霧の場所、あるいは索漠とした場所があって、そこが「よみ」の入り口付近であるのかも知れません。
天国の周辺部と、よみの入り口付近はほぼ地続きになっているか、隣り合わせで、相接しているのでしょう。そこはいわば、天国とよみの"中間地帯"です。臨死体験者はたいていの場合、トンネルを抜けると、その天国とよみの中間地帯に姿を現わすのではないでしょうか。
彼らはすぐに、「光の都」の中に入ったり、あるいは「よみ」の各所に入れられたりするわけではありません。彼らはまず、こうした中間的な場所に置かれるのです。しかしそこは、「光の都」にも近く、それを遠くに眺めることもできる場所です。
苦しみの場所に行ったという人がなぜいないのか
臨死状態になりトンネルを抜け出た人は、美しい場所に置かれたという人が圧倒的に多く、そのほか索漠とした場所に置かれたという人はいるものの、「地獄」に行ったという人や、「よみの苦しみの場所」(ルカ一六・二三、二八)に行ったという人は、まずいません。
ギャラップ世論研究所の所長ジョージ・ギャラップの著した『死後の世界』(三笠書房)においても、臨死体験者のうち自分が不快な苦しい世界に足を踏み入れたと感じた人は、全体の一%に満たないとのことです。
しかし、私たちはこれを怪しむ必要はありません。これは死後には天国だけがあって、よみの苦しみの場所等はない、ということを意味しているわけではないのです。
これには二つの理由があると思われます。
一つは、臨死体験者がトンネル後に置かれる場所は、一般に天国の周辺部、あるいはその辺境部であって、よみの入り口にも近い場所、または天国とよみの中間地帯に違いないということ。
もう一つは、臨死体験者は、もともと天国か"よみの慰めの場所"(ルカ一六・二五)に行くような人々であって、ある理由から特別にこの世に生還することを許された、ということです。
というのは、あとで見るように臨死体験者の中には、生と死の境にあって声を聞き、この世に戻るように言い渡されている人が多くいます。彼らは、この世でまだなすべきことが残されているという理由で、蘇生させられているのです。
臨死体験をして蘇生した人は、神から何らかの使命と期待を込められて、もう一度この世に戻ってきた人だ、と言えるでしょう。もしそのまま死ねば天国あるいは「よみ」の慰めの場所に行けたような人々だが、もう一度機会を与えられて生還したのだと思われるのです。
つまり、天国あるいは「よみ」の慰めの場所に行くような人の中には、ときに生還する人がいて、「臨死体験者」と呼ばれています。しかし、一方で「よみ」の苦しみの場所に行ったような人は、生還せずに単に「死者」となっているわけです。
死んで「よみ」の苦しみの場所に行った人は、多くの場合、神がもう一度人生に戻す必要をお感じにならないのでしょう。それで彼らは「臨死体験者」としては生還せず、「死者」となっています。
しかし、天国や「よみ」の慰めの場所に行くはずだったような人は、新たな使命と期待を込められてこの世に戻る場合があります。彼らが「臨死体験者」と呼ばれているのです。
実際、臨死体験者のほとんどは、体験後の人生を非常に積極的に生きるようになっています。彼らは死がこわくなくなったのみか、その人生において人々と神への愛を非常に大切にするようになっているのです。
これは神が、彼らに"第二の人生"をお与えになったからでしょう。彼らは天国の実在を人々にアピールし、人々の心を見えない世界に向ける一助を果たしています。
なかには、臨死体験をきっかけとして飢え渇くように神を求め始め、クリスチャンになり、牧師にまでなった人々もいます。そして非常に良い伝道をしています。
ある人は「臨死体験には悪霊が関与している」と言いますが、もし悪霊が関与しているなら、このようなことは決して起きないでしょう。
(6) 死者と出会う
臨死体験者の中には、目の前に開けた新しい世界において他者の霊に出会った、と証言している人々もいます。心筋梗塞で死んだ中年の男性は、こう述懐しています。
「突然私は、別の場所にいたのです。一面金色に輝いて、とてもきれいでした。・・・・人もいました。もちろん、人も私たちが思っている形をしているわけではありません」(『続 かいまみた死後の世界』)。
また心停止を経験した十歳の少年はこう言っています。
「トンネルを出ると、たくさんの人が待っていた。みんな、ランプみたいに内側から光っていた。あの場所は、全体がそんなふうに光っているんだ。あそこにあるものは全部、光がいっぱいに詰まっているみたいだった。知らない人ばかりだったけれど、みんなぼくのことが大好きだったみたい」(『臨死からの帰還』)。
一方、知らない人ばかりでなく、知人や近親者を見たという人もいます。ある女性はこう言っています。
「真っ暗なトンネルに入って、そして明るい光の中に出ました。私のそばに死んだ祖父母と父と兄がいて、美しく輝く光が私たちをとり囲んでいました。説明できないような色、この世にはないような色の光でした。人もいました。幸せそうで、三々五々集まっている人もいましたし、学んでいる人もいました。・・・・」(『続
かいまみた死後の世界』)。
福岡県のある男性も、多臓器不全のために臨死体験をしましたが、こう語っています。
「そのとき、わたしの目の前には、沼か川のようなものが広がっていたのです。あたりには、一面に淡いピンク色の花が咲き乱れていました。おそらく、蓮の花じゃなかったか、と思います。
まわりには霧がたちこめていて、はるかかなたに亡くなった祖母の顔だけがはっきり見えるのです。わたしは祖母の方へ行こうとしました。すると祖母の声がはっきり聞こえてきました。『まだ、こちらに来ちゃダメだ。向こうに帰りなさい』みたいなことを、大声で叫んでいたのです」(NHK『臨死体験』)。
臨死体験者は、天国あるいは「よみ」の入り口までは行くので、そこで死者の霊に会うこともあるようです。
(7) 光の生命体に会う
慈愛に満ちた光の生命体
さらに重要なことに、臨死体験者の多くは目の前に開けた新しい世界において、慈愛に満ちた"光の生命体"に会った、と証言しています。子どものころに臨死体験をした中年の女性は、こう語りました。
「庭を見渡しているとき、その人に気づいたんです。その庭はびっくりするほどきれいでしたけど、その人の前では色あせて見えました。私はその人に完全に愛されており、完全に守られていると感じました。あれほど深い喜びを感じたことはありません。何年も前のことですが、今でもあのときの感情を思い出すことができます」(『臨死からの帰還』)。
また、こう語っている人もいます。
「(光の生命体から)『おまえはわたしを愛しているか?』という考えがわたしの心に伝わってきました。はっきりと質問の形をとっていたわけではありませんが、わたしは光が、『もしわたしを愛しているのなら、戻って自分の生涯で手がけたことを完成させなさい』という意味で言ったのだと推測しました。この間ずっとわたしは、深く強い慈愛に包まれているような気持ちがしたものです」(『かいまみた死後の世界』)。
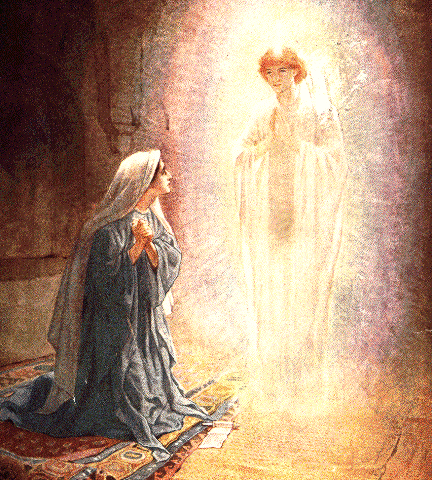
臨死体験者の中には、「光の生命体」に会った、と語る人々が多い。
絵は、イエスの母マリアに現われた天使ガブリエル。ウィリアム・ホール画
この"光の生命体"とは何でしょうか。光の生命体が、「おまえはわたしを愛しているか」という質問をしてきたのであれば、この生命体は神ご自身、またはキリストであると考える人もいるでしょう。実際、そう解釈している臨死体験者も少なくありません。ある臨死体験者はこう語りました。
「私は、その光に到達しようと懸命でした。全然恐ろしくありませんでした。どちらかといえば快適な経験でした。私はクリスチャンなので、あの光とキリストとを即座に結びつけました」(『かいまみた死後の世界』)。
しかし一方で、日本の臨死体験者の中には、この光の生命体を「菩薩」とか「仏」だとか解釈している人もいます。またインドであれば、ヒンズー教の神と解釈している人もいます。これについて、レイモンド・ムーディ博士は言っています。
「死後の世界の体験者たちは・・・・この光の生命が何者なのかという点になると様々な解釈があり、体験者個人の信仰、教育、あるいは信念によって大きく左右されるようである」。
つまり、「光の生命体に会った」という原体験は同じなのですが、それが何者かということになると、体験者の"解釈"が入り込みます。その解釈は、その人の持つ宗教や、バックとなる文化によって左右されているのです。
これは、ある意味では無理のないことでしょう。というのは臨死体験で見る世界は、全く初めて見る世界であり、物質界の様子とは大きく異なっているので、体験者は自分の持つ知識でそれを解釈しようとするからです。
では、これを『聖書』から解釈するとどうなるでしょうか。
光の生命体は天使
聖書から見た限りでは、この光の生命体は、天使(御使い)であるように思えます。というのは聖書は、主イエスの語られた「ラザロと金持ち」の話において、
「ラザロは・・・・死んで、御使いたちによってアブラハムのふところ(よみの慰めの場所)に連れて行かれた」(ルカ一六・二二)
と記しています。死者を迎えるのは、「御使い」つまり天使なのです。とくに「光の天使」(二コリ一一・一四)と呼ばれる者が、死後の世界の入り口において、死者を迎える役を担っているのではないでしょうか。
新約聖書の「使徒の働き」には、使徒ペテロが牢に捕らえられているとき、そこに天使が現われて彼を助けたという記事が載っています。
「突然、主の御使いが現われ、光が牢を照らした・・・・」(使徒一二・七)。
天使は、しばしば光に包まれて現われるのです。臨死体験者の会った光の生命体とは、こうした「光の天使」と思われます。
聖書を見ると、神はしばしば天使を、ご自身の使者として人の前に遣わされています。そして天使を通して語られています。
神は天使に「わたしは・・・・」と言わせ、ご自身の言葉を語られます。この「わたし」は天使ではなく、神ご自身なのです。たとえば旧約聖書・士師記に、こういう記事があります。
「主の使いが来て・・・・樫の木の下にすわった。・・・・主は彼(ギデオン)に向かって仰せられた。『あなたのその力で行き、イスラエルをミデヤン人の手から救え。わたしがあなたを遣わすのではないか』。ギデオンは言った。『ああ、主よ。私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう』」(六・一一〜二三)。
ギデオンと会話しているのは、実際は天使です。しかし、天使は神の口となって、「わたしがあなたを遣わす」と語っています。この「わたし」は神です。ギデオンも、天使を前に、神ご自身に対して語るように語っています。
このように神が人に語られるとき、神はしばしば天使を媒介にして語られます。創世記一八章でも、神はアブラハムと会話していますが、実際はアブラハムの前にいたのは天使で、神は天使を通じてアブラハムと会話されたのです。
また創世記三二章において、ヤコブはペヌエルで「ある人」と格闘しました。ヤコブはこれを神と格闘したことと思いましたが、実際はヤコブが格闘した相手は天使でした。それはホセア書一二・三〜四に、
「ヤコブはその力で神と争った。彼は御使いと格闘して勝ったが、泣いて、これに願った」
と記されていることからわかります。天使と格闘することは、すなわち神と格闘することだったのです。このように、天使はしばしば神ご自身の口となって言葉を語ったり、神の代理として行動したりします。
こうしたことを念頭におけば、臨死体験者がしばしば、光の生命体と呼ばれる天使を「神」と解釈したり、「キリスト」と解釈したりすることがあるというのも、うなずけます。臨死体験において天使は、しばしば神、またはキリストご自身のように死者を迎えるのです。
天使が死者を迎えるという考えは、初期のキリスト者の間でも一般的なものでした。四世紀に記されたキリスト教文学の一つ『パウロの黙示録』(新約外典)には、こう記されています。
「高みに目を向けると、他の天使が見えた。その顔は太陽のように輝いており、また腰に金の帯をしめ、手にはしゅろの枝と神のしるしとを持ち、神の子の御名を記した着物を着ていた。そして、あらゆる優しさと憐れみとに満ちていた。そこで私は天使にたずねて、
『主よ、このように美しく、かつ憐れみに満ちているこれらの者は誰ですか』
と言った。すると天使は答えて言った。
『彼らは正義の天使であって、主を救い主として信じた義人たちの魂を、死に際して連れてくるために派遣されるのです』」(一二)。
このように初期のキリスト者の間にも、天使は人間に対する深い愛情と憐れみに満ちている、との理解がありました。臨死体験者は、この世に戻ろうとしている人々であるので、天使は彼らにとりわけ深い愛情を示すのです。
また、天使はもともと人間に「仕える者」として造られましたから(ヘブ一・一四)、人間に対して親密な友のような態度を示すこともあります。ある臨死体験者はこう語りました。
「あの光が私に語りかけたその時から、私はとても良い気分になったのです。安全で愛されている感じです。あの光から流れ出す愛は、想像を絶するもので、説明のしようがありません。同席するのが楽しい人でした! おまけにユーモアのセンスもあるのです・・ほんとうですよ!」(『かいまみた死後の世界』)。
また、子どものころ高熱を出して"死んだ"女性はこう語っています。
「私はそちらに向かって歩きだしました。しばらくすると、すぐそばに白い光のようなものがいるのを感じました。親しげで、ちっとも怖くはありませんでした。その光が『どこへ行くの?』と聞くので、『あっちに行くのよ』と答えると、『それはすごいな。じゃ、いっしょに行こう』と言うんです。見たこともない花がたくさん咲いていました。私はその光に花の名前を聞いたり、花を摘んだりしながら歩いて行きました」(『臨死からの帰還』)。
これを語った女性は、臨死体験をした時には九歳でした。天使は、子どもに対しては子どものように、大人に対しては大人のようになって、愛情をもって接してくれるようです。
(8) 生涯を回顧させられる
臨死体験者の中には、光の生命体の前で自分の生涯を回顧させられた、と述懐している人々が多くいます。二三歳のときに臨死を経験した女性は、こう語っています。
「その光の存在は私を包み込み、私の人生を見せてくれました。これまでしてきたことをすべて見て、反省するわけです。中には見たくないこともありますけど、みんな終わったことだと思えば、かえってほっとします。
とくによく覚えているのは、子どものころに、妹のイースター・バスケットを横取りしてしまったことです。その中のおもちゃが欲しかったものですから。でも、あの回顧のときには、妹の失望やくやしさを自分のことのように感じました。私が傷つけていたのは私自身であり、喜ばせてあげていたのも、やはり私自身だったのです」(『臨死からの帰還』)。
また、ある臨死体験者はこう語っています。
「そのときフラッシュバック(生涯の回顧)が始まったのです。・・・・(回顧をしているとき)あの光は時々コメントを加えました。・・・・私の生涯におけるいくつかの出来事を回顧させ、わたしが思い出さずにはいられないように目の前に提示してくれたのです。その間ずっと、あの光は愛の重要性を強調していました。・・・・
あの光は、他人のために何かを行なうように、最善を尽くすように務めなさいと指摘しました。・・・・また、知識に関することにも強い関心を寄せているようでした。
あなたはこれからも勉強を続けることになる・・・・(このころまでにあの光は私に、あなたは現世に戻っていくことになると言っていたのです)、常に知識の追求を行なわなければならないと言いました」(『かいまみた死後の世界)。
こうした証言から察する限り、光の生命体による生涯の回顧は、生還しようとしている臨死体験者に対して、何らかの教育的配慮でなされているように思えます。
生涯の回顧は、見ている本人に、しばしば強い反省を起こさせます。次のように語っている臨死体験者もいます。
「あらゆることが同時に浮かび上がったのです。母親のことや、自分が犯した過ちについて考えました。・・・・あんなことをしなければよかったと思ったし、戻って償いをしたいと思いました」(『かいまみた死後の世界』)。
「やり終えることができずに残念に思うこともありました。このフラッシュバックは、心象の形をとっていたといえるかと思いますが、いわゆる普通のものよりもずっと鮮明でした。
わたしは主な出来事をみただけなのですが、すべてが大変な速度で浮かび上がってくるので、数秒で自分の一生をすっかり見てしまったように思えました。・・・・しかしその映像を充分見ることも、理解することもできました。・・・・
この体験をしている間ずっと、力強く愛に満ちた生命が、私のすぐそばにいることがはっきり感じられました」(『かいまみた死後の世界』)。
(9) 生と死の境に立って、どちらに行くかの決定をする
その後、臨死体験者の多くが、生と死の境に立って、この世に戻るように言い渡されています。臨死状態から帰還した心臓病専門医はこう語っています。
「その人(光の生命体)は私に、あなたは帰らなければならない、あなたにはまだやらなければならないことがあるから、と言うんです。やがて、私は吸い込まれるように肉体に戻ってゆきました。・・・・気がつくと、私は横たわって、手に(蘇生のための電気ショック用の)電極を持った医師を見上げていました」(『臨死からの帰還』)。
また、ベトナムでの戦闘中に"死んだ"ある軍曹は、こう語っています。
「『神様、私は死にたくありません』と頭の中で叫んでいました。すると私の頭の中に『大丈夫だ』という声が聞こえてきたのです。『お前はまだ死なない。ここにはまだ来なくてよい』と私に話し聞かせていました。
次の瞬間、意識を回復すると、私のまわりを囲んで泣いている仲間たちが見えました。その一人が驚いて、『君は死んでいたはずなのに!』と言ったのです」(NHK『臨死体験』)。
子どものころに臨死体験をした女性は、こう語っています。
「八つのとき、プールで溺れかけたことがあるんです。底なしの真っ暗な穴に落ち込んだようでした。すると突然、明るい光が現われて、とても安らかな気持ちになったんです。その光と話をして、このまま光の中にとどまりたいと言い張りました。でも、あなたにはやらなければならないことがある、と言われました。そして、私はこの世に戻ってきたんです」(『臨死からの帰還』)。
また、帰るように光の生命体から言われるのではなく、死んだ近親者を通して言われたと証言する人もいます。臨死状態におちいったある母親はこう語っています。
「霧の向こうから叔父のカールが現われました。叔父は何年も前に死んでいました。叔父は私の行く手をさえぎり、『戻るんだ。現世でのおまえの仕事はまだ完成していない。戻りなさい。すぐに』と言いました。
私は戻りたくなかったけれど、どうしようもありませんでした。あっという間に、私は自分の物理的肉体の中に戻っていました。・・・・そして私の小さな息子が『神様、お母さんを返してください」と泣き叫んでいる声が聞こえたのです」(『かいまみた死後の世界』)。
この人の場合、帰るように言ったのは近親者でした。しかしその直後に実際に肉体に戻っているのを見ると、神が何らかの配慮から、死んだ近親者を用いて彼女に帰るように告げさせたのだ、とも理解されます。
いずれにしても、臨死体験者は生還する前に、この世に帰るように言い渡されていることが多い、という事実は興味深いことです。彼らは、そう言い渡された直後に実際に生き返っているのです。
これは、彼らの体験が幻覚ではなく、事実であったことを示すもう一つの証拠ではないでしょうか。
臨死体験者は死後の世界の一部を見たが、全貌を見たのではない
臨死体験者は一般に、死の体験を通して神からの取り扱いを受け、新しい使命と機会を与えられ、期待を込められて世に戻ってきた人々である、と言えるでしょう。
人は死ぬと、天国あるいは「よみ」の各所に行きます(二コリ五・八、黙示二〇・一三)。しかし臨死体験者は、神からの特別な恵みを受けて、天国の周辺部、あるいは辺境部、また「よみ」の慰めの場所の入り口付近の光景を見る機会を得、そののちに生還しています。
臨死体験者となった人々は、死後も魂は肉体を離れて存続すること、死後の世界は存在すること、神と人を愛する者たちのために素晴らしい場所があること、神は天使を通じて私たちに深い愛情を示されること、さらに、地上の人生にはそれぞれ重要な使命があること、などをあかししています。彼らの証言は、死後の世界の研究のために重要な資料と言えるでしょう。
聖書の正しい理解と、臨死体験の間に、根本的な矛盾はありません。臨死体験の適切な研究は、聖書のいう死後の世界をより明確にする一助となるでしょう。
とはいえ、臨死体験者の見てきた世界は、死後の世界の一部であって、その全貌ではありません。死後の世界は、臨死体験者の見た世界よりも、実際にはもっと大きな広がりを持っています。
臨死体験者の証言だけから死後の世界の全貌を明らかにすることはできません。死後の世界に関してバランスある理解を私たちが持つためには、聖書の記述を中心に研究していくことが不可欠なのです。
久保有政 著
|

 死後の世界
死後の世界