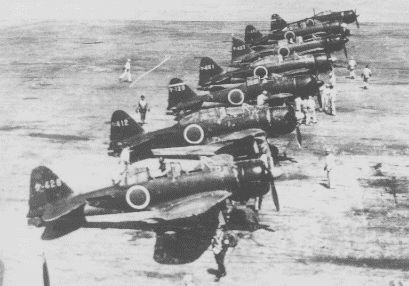死者を弔う心
それは亡き人々の心を汲んで生きることである

盆踊り。日本の文化は生者と死者
が織りなす文化だと言われる。
[聖書テキスト]
「この人々はみな、その信仰によってあかしされましたが、約束されたものは得ませんでした。神は私たちのために、さらにすぐれたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかったのです。
こういうわけで、このように多くの証人たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも、いっさいの重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競走を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスは、ご自分の前に置かれた喜びのゆえに、はずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました」 (ヘブル人への手紙一一章三九〜一二章二節)
[メッセージ]
今日は、この箇所から「死者を弔(とむら)う心」と題してご一緒に恵みを受けたいと思います。
私は時々、かつてお世話になった小林千恵子先生のことを思い出します。私が先生に初めてお会いしたのは、先生がもう九〇歳くらいになられた時でした。先生は頭は美しい透き通るような白髪をしていらっしゃいました。
千恵子先生は、九州の由緒ある古い神社の宮司の娘。でもクリスチャンになって、勘当されて家を出て、牧師の妻になりました。そしてただキリストだけに仕えて、伝道生涯を送ってこられたのです。私があるとき、死後の世界のことで教会でメッセージをしますと、ものすごく喜んで下さって、「よく語って下さった。大切なメッセージです。教会はもっとこのことを知らなくてはいけません」と励ましてくれたものです。
しかしもうその千恵子先生は、この地上にはいません。天に帰られました。
また、私が大学生の時のことでした。池袋の地下道で、浮浪者の方々の中に松葉杖の人を見つけました。話しかけてみると、とてもいいかたでした。しかし病気のようだったので、近くの病院に連れていきました。足がむくれていたのです。診察してくれたお医者さんは、
「肝臓を病んでいます。ここに来るのがあと一週間も遅かったら、手遅れになっていたところでした」
と言いました。私は時々看病に行きながら、イエス様の福音を伝えました。あるときは主にある二人の兄弟姉妹と共に行って、病室で讃美歌を歌ってあげました。彼はとても喜んでくれました。何ヶ月かして、病院を退院した彼は、注文紳士服をつくるお店に努めていました。彼にはそのような技術があったのです。私が訪問してみると、「これが私がつくった紳士服です」と見せてくれました。それは素晴らしい仕立ての背広でした。
そのときの嬉しそうな顔を今も忘れることができません。それが、彼と会った最後でした。その翌年、彼が病院で亡くなったという知らせを、人づてに聞きました。肝臓病をこじらせたとのことでした。彼もまた、もう地上にはいません。思い出だけが私の心に残っている。思い出だけ――そう思ったこともあります。
けれども、そうではないのです。単なる思い出だけではない。私はそれ以上のことを感じます。私の感覚の中では、彼らは私の近くにいるのです。今お読みした聖書の一二章一節に、
「このように多くの証人たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから……」
と書かれています。雲のように、私たちのまわりには先輩たちが取り巻いてくださっているという。ユダヤ人には、そういう意識があったんですね。死者の霊、また先祖の霊が、雲のように私たちを取り巻いているという。この感覚は日本人には、よくわかるのではないでしょうか。
日本の文化は生者と死者が織りなす
かつて明治時代に、欧米の人たちが日本にやって来たとき、彼らが日本人を見てとても驚いたことがあります。それは日本人が、あたかも死者の霊、先祖の霊と共に生きているように見えたというのです。
日本人は、夏にはお盆をします。先祖の霊を自宅の庭に迎えて、弔い、また家族団らんの時を持ちます。そこには先祖たちの霊も一緒にいる。生者も死者も共に家族一緒になって団らんの時を過ごすのです。あたかも日本人は、死者の霊と共に生きているようだ。また日本人は、神棚や仏壇に食べ物や水など、先祖供養のお供え物をして、死者と共に暮らしている。
それでラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は、そうした日本人の生き方にとても感銘を受けて、日本を「死者の国」と呼びました。これは、日本人は死者の霊と共に生きている人たちだ、という意味です。
ある人は、日本の文化は生者と死者が共に織りなしてきた文化だ、と言いました。
欧米人の感覚だと、死者はもう交流できない遠い別世界へ行ってしまったという感覚です。仮にビルディングでたとえるなら、たとえば私たち生者はこのビルにいるとして、死者は別棟のビルにいる。だから、両者は簡単には交流できない。
でも、ユダヤ人や日本人の感覚では、この世とあの世はつながっているのです。死者は雲のように今も私たちを取り巻いて見てくれている。近くにいるんですね。
民族学者の柳田国男によれば、日本人は昔から、死んだ親族の霊は、生きている者の近くや、裏山に住んでいると考えていました。
たとえば京都では、毎年お盆の送り火に、山で「大文字焼」をしますね。あれは、お盆のときにやってきた死者の霊を、裏山へお送りするための火なのです。京都市内に行ったことのあるかたは、わかると思いますが、京都の街は周囲を山で取り囲まれています。その山に死者の霊が住んでいるという感覚です。

大文字焼。死者の霊を裏山へ送る行事である。
ちょうどそれと同じように、聖書の「ヘブル人への手紙」の著者は、私たちの先輩、先祖の霊は、ちょうど競技場の観客席からみるようにして、私たちの周囲を取り囲んで見ている、というのです。ユダヤ人にとっても、日本人にとっても、先祖の霊、死者の霊は雲のように取り巻いて近くにいてくれる存在なのです。
私はこの感覚は、生きる上でも信仰生活の上でも、非常に重要だと思っています。
イエス様はあるとき、
「あなたがたの父アブラハムは、わたしの日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て、喜んだのです」(ヨハ八・五六)
と言われたことがあります。イエス様が今から二〇〇〇年前に地上に来られて、地上を歩まれた。イスラエル民族の父祖アブラハムは、死後の世界から、このイエス様を見たのです。
救い主イエス様が実際に地上に来て、そこを歩まれたのを見て、アブラハムは大いに喜んだというのです。イエス様はこのように、つねに雲のように取り巻いている死者の霊、先祖の霊を意識して生きておられました。
このヘブル人への手紙で言っていることも、またそうなのです。この聖句の前の部分を読みますと、イスラエルの父祖たちの歴史がずーっと書いてあります。
アベルから始まって、エノク、ノア、アブラハム、サラ、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、そのほかイスラエルの先輩たちのことが次々と書かれています。その上で、
「このように多くの証人たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから……」
と言われているのです。彼ら先輩たちは、雲のように私たちを取り巻いてくれている。だから、それを意識して歩んでいこう、という教えです。それを感じながら生きていこう、という教えです。
彼らはなにか遠い別の場所に行ってしまったのではない。私たちのすぐ近くにいて、後輩である私たちの姿を身近に見ては、あるときは喜び、あるときは嘆き悲しんでくれている。そういうのです。
この感覚は、信仰生活の上で、とても大切です。私たちも死者の霊、先祖たちの霊を身近に意識しながら生きていくのです。
敬虔な思い
私はときおり、自分という人間は一体何だろう、と思います。あるとき、町を歩いていて、ふと思いました。
「自分は今この町を歩いているけれども、この私も、またいま私の目に入っているすべての人々も、一〇〇年前はいなかった。そしてこの町には、まったく別の人々が歩いていた。彼らは今、死者になっている。それでは彼ら死者たちと、今生きている私たちとの違いはいったい何なのか」
生者と死者の違い――両者は全く違うもののように思うかもしれませんが、本当は大きな違いはないのです。単に今地上にいるかいないかだけの違いです。私という人間は、生者と死者の連綿としたつながりの中の、一つの鎖の輪にすぎないということです。映画でたとえるなら、一つの映画フイルムの一コマにすぎない。
なぜなら、いま死者となっている者も、かつては生者であった。また、いま生者である私もいずれ死者となります。それぞれが一つの鎖の輪にすぎない。映画のフイルムの一コマです。ずーっと続いている中の一部分なのです。死者の霊を意識しながら生きる、先祖たちの霊を意識しながら生きる、というのはそういうことです。先祖から子孫に続く一連の流れの中の自分というものを感じるのです。
私の両親はすでに他界して亡くなりました。家内の両親もそうです。彼らはすでに死者となっています。でも、遠くに行ってしまった気がしません。雲のように身近にいて見てくれている気がする。私は聖書のこの御言葉を読むとき、非常な慰めを受けるのです。死者は遠い世界のものではない。彼らの世界とこの地上界はつながっているのだ、ということです。
私はまたこのことを思うとき、非常に敬虔な思いが心の中にわいてきます。見えないが、私たちとつながりのある霊が、私たちを取り巻いて存在している。みなさんは、どうですか。そうした「死者の霊たちを思って敬虔な気持ちになる」という意味がおわかりでしょうか。
「いや、そんな敬虔な気持ちなんてわきません」「あなたが何を言っているのか全く理解できません」というかたがもしおられるなら――ときどき左翼にはそういう人たちがいますが――私は、そういう人を信用しません。それでも人間なのかと思います。
一二月八日の意味
一九四一年一二月八日といえば、日本が大東亜戦争(太平洋戦争)の開戦を決断し、戦争が始まった日です。真珠湾攻撃の日でもあります。
ハワイというのは、昔カメハメハ王朝というのがあって、一つの王国を形成していました。王様がいて、人々は平和に暮らしていました。しかし武力を持たない国家の悲哀。そこにアメリカ軍が乗り込んできて、乗っ取ってしまいました。
アメリカは星条旗に星を一つ増やしてそこに立て、ハワイをアメリカの領土となしました。そして、ハワイの真珠湾に軍事基地を建設しました。それはアメリカのアジア侵出のための拠点だったのです。日本はその軍事基地を叩きました。
多くの人は終戦記念日の八月一五日を記憶しますが、私はそれ以上に一二月八日が重要だと思っています。その日、日本は自存自衛と、アジア解放のための戦いを開始しました。かつてタイのククリット・プラモード元首相は、戦後「一二月八日」と題する詩を書きました。
「日本のおかげで、アジアの諸国はすべて独立した。日本というお母さんは、難産して母体をそこなったが、生まれた子供はすくすくと育っている。今日東南アジアの諸国民が、米英と対等に話ができるのは、一体誰のおかげであるのか。それは身を殺して仁をなした日本というお母さんがあったためである。一二月八日は、われわれにこの重大な思想を示してくれたお母さんが、一身を賭して重大決心をされた日である。われわれはこの日を忘れてはならない」

プラモード・タイ元首相。「日本のおかげで、
アジアの諸国はすべて独立した」
一二月八日は大東亜戦争の始まった日です。東亜とは東アジアのこと、大東亜は、それに南洋諸島などを加えた地域のことをいいます。大東亜戦争はこの地域で戦われた戦争の意味なのです。それは史上空前のスケールの戦いでした。
それは日本の自存自衛とともに、白人支配からアジアを解放するためのものでした。
その戦争で、日本人は兵士・民間人を合わせて約三一〇万人が犠牲になりました。四年間続いた戦いで、当初は日本は破竹の勢いでアメリカ軍やイギリス軍を破っていきました。しかしやがて、資源のない日本は物資が尽きてしまった。戦いの後半は、物量にものをいわせたアメリカ軍の前に、日本はやがてどんどん負けていきました。日本兵の多くは、戦場で死を前にしたとき、戦友たちにこう言って亡くなっていきました。
「靖国で会おう」
ほとんどの兵士たちがそう言って死に就きました。日本人にとって靖国神社とは何かというと、「そこに行けば、死んだ戦友に会える」「日本を守るために命を投げ出してくれた人々に会える」「英霊たちに会える」という場所だったのです。
「靖国で会おう」――このような言葉を兵士が言って死んでいった国は、おそらく日本だけでしょう。そこに行けば会える、という場所を持っている。それは単なる墓ではないのです。靖国神社は、明治時代に作られたものですけれども、そこには、国を守るために命を捧げてくれた人々に対する心からの弔いを表そうとする日本人の気持ちがあらわれています。
終戦後、アメリカの占領軍GHQが、日本を占領しました。占領軍にとって、靖国神社は得体の知れない存在でした。彼らにとって靖国神社とは、軍国主義と神秘主義の統合した教えを広めるカルトの神殿のようなものに思えたのです。
ですから初め、占領軍は靖国神社を焼き払おうとしました。ところが、そのとき反対してくれた人がいたのです。誰だと思いますか。カトリックの神父さんです。駐日ローマ教皇庁代表のブルノー・ビッテル神父でした。彼は言いました。
「いかなる国家も、その国家のために死んだ人々に対して、敬意を払う権利と義務がある。……もし靖国神社を焼き払ったとすれば、その行為は米軍の歴史にとって不名誉きわまる汚点となって残ることであろう。……はっきり言って、靖国神社の焼却、廃止は米軍の占領政策と相容れない犯罪行為である。……国家のために死んだものは、すべて靖国神社にその霊を祀られるようにすることを、進言する」
この神父さんの言葉で、靖国神社は救われたのです。クリスチャンが靖国神社を救いました。私はこのことで、ビッテル神父に深く感謝しています。なぜなら、もし靖国神社を焼き払ったならば、日清、日露、また大東亜戦争で散っていった多くの日本人たちの気持ちを踏みにじったことになったでしょう。そうしたら、その後の日本はどうなっていたかわかりません。

靖国神社を焼き払おうとするGHQの姿勢に、
待ったをかけてくれたのはカトリックの神父だった
死者の思いを汲む
以前、『おじいちゃん、戦争のことを教えて』(小学館文庫)という本が、ベストセラーになりました。これはアサヒビールの名誉顧問・中條高徳さんが、アメリカに留学中の孫娘からの質問に答えて語ったものを、本にしたものです。いい本なので、みなさんにもお勧めします。あの戦争とは何だったのか、それが非常にわかりやすく書かれています。自虐史観でない、健全な歴史観で書かれている。アメリカの悪いところも、日本の悪いところも公平に書いてあります。中條さんも、靖国神社に行くと、死んだ戦友たちに会える気がするといいます。そして、
「私が生きていて申し訳ない」
という気持ちにもなる。また、生きている者としての責任を果たさなければならない、という心がわいてくるといいます。それが日本人の心なのです。死者の霊、先祖の霊が「雲のように私たちを取り巻いている」という聖書の言葉は、日本人にはよくわかります。私たち日本人は、そういう霊的な生き方というものを、小さい頃からつちかわれているのです。
ルカの福音書一六章に、イエス様がお語りになった「ラザロと金持ち」の話があります。ふたりとも死んで、陰府に下りました。ラザロは、陰府の慰めの場所へ行きました。金持ちは陰府の苦しみの場所へ行きました。しかし金持ちは、陰府の苦しみの中で、今も地上にいる兄弟たちのことを心配しています。金持ちは、慰めの場所にいるアブラハムに向かって叫びました。
「アブラハム様、どうかラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が五人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないように、よく言い聞かせてください」。
私はこの箇所を読むたびに、深い感動を持ちます。この金持ちは死者です。しかし、死者の世界で、地上の人々のことを思い、心配してくれているのです。死者の世界で私たちのことを心配してくれている人々がたくさんいます。
私は、あの「靖国で会おう」と言って祖国とアジアのために死んでいった人たちが、今の日本を見たら、いったいどのように思うだろうか、と思って胸が痛くなることがあります。
私たちは、彼らの精神を汲んで生きているだろうか。
ある人たちは、「日本が戦争なんてバカなことをしたからだ」と言うでしょう。しかし、そんな簡単なものではありません。あの残酷きわまりない弱肉強食の世界の中で、はたして誰が戦争を止めることができたか。
あれは歴史の必然だったのです。誰も止めることのできない流れの中に、否応なく日本は置かれていました。そうした中で、ぎりぎりの選択をした人々、また苦悩の中に生き、死んでいった数多くの人たちがいます。
温室育ちの現代に生きる私たちが、過去の人々の歴史を裁くことはできません。平和ボケした私たちが「戦争はいけません」といって過去の人を裁いても、それは何の意味もないことです。私は当時の人々の書いたものをいろいろ読みましたが、政治家も、また軍部の人たちでさえも、日本人は何とかして戦争を避けようとしていました。それでも戦争に巻き込まれていった。当時はそういう世界だったのです。
いずれにしても、彼らの生と死があったからこそ、今の私たちがあるのです。
真珠湾攻撃の真実
以前、日本のキリスト教のある教派で、「日本がかつて真珠湾攻撃をしたことをアメリカに謝罪しよう」という案が、会議で通りそうになったことがあります。しかし、そのときある牧師が反対してくれたので、結局その案は通りませんでした。
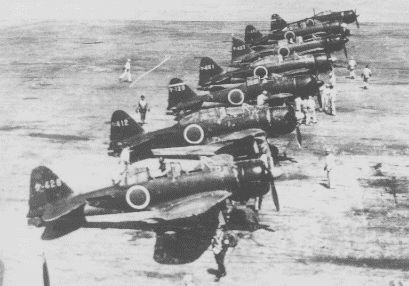
真珠湾攻撃にも参加した零戦
私はその話を聞いて、嘆かわしいことだと思いました。まだまだ、アメリカが一方的な正義で、日本は悪者だったという不健全な観念が、教会にも巣くっているのです。歴史を知らないとは恐ろしいことです。なぜ真珠湾攻撃が起こったのか、その本当の歴史は次のようなものでした。
当時日本は、アメリカとの戦争は何としてでも避けたいと思っていました。そして何度も、外務省を通じてアメリカとの和平交渉を粘り強く続けていました。しかし、日本は平和を望んでいたのに、アメリカ側にはその気はなかったのです。アメリカには「オレンジプラン」というのがありました。国をいろいろ色分けしていて、日本はオレンジだった。
オレンジプランとは、中国にアメリカの利権を獲得するために、東アジアの黄色人種の大国・日本は邪魔なので、制圧し、いずれ叩きのめそうとするアメリカの長期的な対日戦略だったのです。そしてオレンジプランには、なんと最終的に日本の本土を爆撃し、日本を壊滅させることまで盛り込まれていました。大東亜戦争の前や、大東亜戦争中のアメリカの行動はすべて、このオレンジプランに基づいて行なわれたものなのです。
オレンジプランによって、アメリカのルーズベルト大統領は、日米戦争を始めることを願っていました。そして日本を叩きのめして、中国に利権を獲得したいと。しかし当時のアメリカ国民はどうかというと、戦争に反対でした。ではどうしたら、アメリカ国民を戦争に向かわせることができるか。
アメリカは、西部劇でみられるように、決闘の国です。自分から銃を抜くのではなく、相手に先に銃を抜かせなければなりません。だから、もし日本側が最初の一発を打てば、アメリカ国民も戦争やむなしと思うでしょう。
それで、日本に最初の一発を打たせるために、アメリカが日本に突きつけたのが、ハル・ノートと呼ばれるものでした。それは日本が絶対に呑めないような無理難題を書き連ねた要求書でした。アメリカ議会も、アメリカ国民も全く知らないところで、ひそかに日本の外務省に渡されたのです。
それはまさしく日本に「死ね」という内容でした。しかも、それはそれまでの何ヶ月もの和平交渉を全く無視した内容で、それを読んだ日本は、目がくらむほどの絶望感に襲われたのです。そして、
「事態ここに至る。座して死を待つよりは、戦って死すべし」
という気持ちから、真珠湾攻撃に踏み切りました。ちょうど窮地に陥れられたネズミが、ネコに向かって牙をむいたような出来事です。
その際に交わされた日本軍の無線連絡は、すべてアメリカ側が傍受していました。アメリカはすでに日本の無線の暗号も解読していて、日本が真珠湾を攻撃するということも知っていました。しかし、ルーズベルト大統領は、それを真珠湾にいるアメリカ軍にわざと伝えなかったのです。そして日本が真珠湾を攻撃したというニュースが飛び込んだとき、アメリカの大統領は「ほっとした表情をみせた」と、側近が語っています。
日本が最初の一発を打ってくれたことを心から喜んだのです。翌日、ルーズベルト大統領は、アメリカ国民に向けて劇的な効果を考えつくした演説を行ないました。
「日本のだまし討ちを忘れるな。屈辱の日を忘れるな」
と、そう言って日本人の暴虐を訴え、アメリカを戦争に向かわせていきました。こうしてアメリカ全土に「リメンバー・パールハーバー」の声が踊ったのです。その後、真珠湾の司令官であったキンメル海軍大将と、ショート陸軍中将は、真珠湾の責任を問われ、「職務怠慢」の烙印を押され、軍から追放処分となり、失意のうちに世を去りました。
その五九年後、西暦二〇〇〇年にアメリカ議会は、当時のアメリカ政府が日本軍の動きを察知していながら、それを現地の真珠湾に教えていなかったことが敗北の原因だと認定して、二人の名誉を回復する決議を採択しました。しかし、そのときは二人ともすでに死んでいたのです。彼らは利用されて、捨てられました。そして死後になって、ようやく名誉が回復されました。
イエスさまはこういう事実をどう見られるか、と思います。私たちは「アメリカは正義で、日本は悪者だった」と聞かされてきましたけれども、そういう主張の中にひそむパン種に気づくべきなのです。
日本人の心
私は日本人の名誉も回復したいと思います。
真珠湾攻撃は、日本が好きこのんでやったものではありませんでした。あの残酷きわまりない弱肉強食の世界で、それは追いつめられた者の最後の最後の選択だったのです。
アメリカは、中国を欲しいがために日本をことさらに敵視し、戦争を望むという過ちを犯しました。真珠湾攻撃は、それまでの長い歴史の積み重ねの一つの結果として起こったものです。日本とアメリカはいつかはぶつからねばならなかった。
以前、アルカイダのテロリストが旅客機をのっとって、ニューヨークの世界貿易センターに突っ込み、大惨事を引き起こしたことがありました。そのときアメリカのマスコミは、それをかつての日本の真珠湾攻撃になぞらえました。
しかし、テロリストのやったことと真珠湾攻撃とは、全く性質の異なるものだったのです。旅客機の乗っ取りや世界貿易センタービルの破壊は、民間人の大量殺戮を目的としたものでした。一方、真珠湾攻撃は、真珠湾の軍事基地破壊をねらったものです。軍事施設の隣りには、市街がありましたが、市街は全くの無傷でした。
ここで、真珠湾攻撃の際に戦死した日本海軍の飛行兵曹長、長井
泉さんの遺書を少しご紹介したいと思います。彼は死んだとき、ちょうど二〇歳の若者でした。彼は自分の死を予感して、こんな言葉で親への手紙をつづりました。少し現代的な言葉使いに直させていただきますが、こう書いています。
「男子と生まれ、皇国に生を受け、しかも軍人として屍を戦場にさらすことは軍人の本望とするところです。……このたびの戦は、一挙に終わるものでもなく、東洋平和確立までには、どれほどの苦難があるか測り知れません。この世に生を受けて二〇年余り、慈愛の胸に抱かれ、何一つとして不自由な思いをしたこととてありません。わがままばかりを申して今日まで心配をおかけし、一度の親孝行のまねごとさえ出来ず、老後の面倒さえ見ることもできず、先立つことは何よりも心残りに思っております。
しかし、この国家存亡のときに、私情を云々することはできず、祖国の恩に報いてまいる覚悟です。かねてから父上が言われていた教え、国家のために死ぬことこそ最大の親孝行、を心に銘記し、必ずや、これという勲功は立てずとも、決して他人に遅れはとらぬよう最後のご奉公をしてまいります。なにとぞ、先立つ罪をおゆるしいただきたく、ご両親におかれましても、すでに私亡き時の覚悟は充分あられるとは信じておりますが、決してお嘆きなさいませんよう。もし報が入れば、『せがれは良くやった』と、まずおほめ下されたく存じます。とくに母上は体も病弱ゆえ、お嘆きのあまりに寿命を縮めたりなさいませんよう」
そして彼は、最後にこの和歌を書き添えました。
「身はたとえ太平洋に水漬(みづ)くとも留め置かまし大和魂」
「今さらに驚くべきもあらぬなりかねて待ちこしこの度の旅」
死を「旅」ととらえ、「今さらに驚くべきことでもない」「かねてから待っていたものだ」と言って、祖国とアジアの防衛のために彼は胸を張って、散っていったのです。
しかし、太平洋の藻屑(もくず)となり、太平洋の水滴となっても、彼の大和魂はこの日本に生きている。彼の霊は祖国に戻ってきて、日本をおおう雲の一滴一滴の水滴となってくれている。これが日本人の死生観なんですね。そうした大和魂の死者の霊が、雲のようにおおっているのが、この日本という国です。
こういう手紙に現われた精神を、現代の人々はなかなか理解しません。とくに左翼の人たちは、軍国主義の犠牲者だとか、狂信的な神国思想の犠牲者だとか言いますね。しかし、そんなものではない。
この手紙に表れているのは、きわめて冷静で、バランスのとれた健全な精神です。そして死の恐怖を乗り越えながらも、なお両親の身を案ずる思いやり深い心です。そして祖国を思う心。
当時の日本は、そういう人々で満ちていました。私たちを雲のようにおおう死者の霊、先祖の霊は、きわめて愛情深い霊です。私はそれを思うとき、
「安らかに眠ってください」
と心の中で繰り返します。死者をさばくのではない。死者を弔う心を、私自身が死者になるまで持ち続けたいと思います。
もののあはれ
日本には昔から、「もののあはれ」という言葉があります。もののあはれの心は、非常に日本的なもの、日本文化の根底にあるものです。イエス様はあるとき群衆を見て、
「彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深くあわれまれた」(マコ六・三四)
と聖書に書かれています。これが「もののあはれ」です。日本人にはよく理解できるものです。
「もののあはれ」とはまた、たとえば一瞬美しく輝いたのち、消えていくものなどを見たとき、「きれいだ」と思うけれども、同時にそのはかなさを深く心に感じて、「哀れだ」「かわいそうだ」とも思う。そういう胸がしめつけられるような思いが、「もののあはれ」です。
生きとし生けるものの運命は過酷。でも、あるいはそれだからこそ、精一杯に生きようとするものを、まのあたりにするとき、同じ生き物として、共感と尊敬と愛情の念で胸が詰まる思いをします。もののあはれの心。死者のことを想って「安らかに眠ってください」という祈りは、そこから出てきます。同じ、はかない生き物である私たちが、死者を想って「安らかに」と願う。これは人間としてとても大切な感情だと思います。
私たちのまわりには、雲のように先祖や先人たちの霊が取り巻いています。私たちは彼らのことを思い、「安らかに」という願いを持ち続けたいものです。
この東京はとくに、かつてホロコーストのあった街です。ホロコーストというのは、何もナチスの専売特許ではありません。かつてアメリカ軍は東京大空襲をして、東京の民間人を約一〇万人殺しました。上智大学の渡部昇一教授は、かつて外国で日本のことを紹介するとき、
"Tokyo is a holocausted city" (東京はホロコーストされた街)
と英語で言ったことがあるそうです。事実、東京大空襲はホロコーストでした。

大空襲後の東京。ホロコーストされた街である。
武器を持たない民間人を殺すというのは、ひどい国際法違反です。しかし、アメリカはそれを計画的に大量にやりました。東京以外の都市でもやりましたので、全部で六〇万人くらい犠牲者が出たといわれています。東京も全部焼け野原になりました。その直後の東京は、どこからも富士山がよく見えたそうです。いまの東京はどこもビルばかりで、富士山はなかなか見えませんが。
アメリカ軍の空襲のやり方は、一辺が五、六キロの範囲に焼夷弾をまず落として、炎の壁をつくります。そののちその中に爆弾を雨あられと落とすのです。逃げ場を失った人々はその中でみな焼け死にます。
東京の川などは、焼けこげながらも水を求めた人々の死体で詰まり、赤く血に染まったといいます。それは想像を絶する地獄絵図だった。このように、東京大空襲というのは軍事施設をねらったものではなく、最初から民間人の大量虐殺を目的としたものでした。
そうした史上空前のスケールの犯罪が行なわれたのです。ナチスのユダヤ人虐殺に匹敵する戦争犯罪です。そのような大量の死者を出した地であることを思うときに、もののあはれを感じない人がいるでしょうか。この世界は、羊飼いのいない羊たちの群れのようなのです。私たちは、もののあはれを想い、「安らかに眠ってください」という気持ちを抱くとともに、いま生かされている私たちの責任をも深く感ずるのです。
当時の人々は、このように日本人が虫けらのように殺されている事実を目の当たりにしていましたから、特攻隊を出してまでも、また特攻隊に自ら志願してまでも、祖国を守りたいと思って戦い続けたのです。
このままだったら、祖国は滅びてしまう。自分の愛する人々もみな殺されてしまう。だから、私が捨て石になります。そのような思いです。私たちは、そのような先人たちの祖国思いを理解しているでしょうか。もののあはれ、悲惨な物語がたくさんありました。死者を弔う心とは、彼らの祖国思いを自分たちも持つことです。
私たち抜きに彼らが全うされることはない
私たちの先祖、また日本人の先輩たちは、必死な思いで、この日本という祖国を残してくれました。大切なのは、私たちは彼らが築いた歴史の流れの中に立っている、ということです。そうした歴史の遺産を受け継ぐ者としての責任が、私たちにあります。
生きている者としての責任。死者たちがバトン・タッチして渡してくれたものを守り、全うしていく責任なのです。ヘブル人への手紙の著者は、ここで何を言おうとしているのでしょうか。アベルから始まって、イスラエルの歴史を受け継いできたいろいろな人々のことを語ったのちに、こう言っています。
「この人々はみな、その信仰によってあかしされましたが、約束されたものは得ませんでした。神は私たちのために、さらにすぐれたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかったのです」(一一・三九〜四〇)。
過去の死者たち、先祖たちも、私たちを抜きに「全うされる」ことはない、というのです。私たちは、過去の人々が残してくれたものをしっかり受け継いで、それを完成させていく責務を負っていると。
私たちクリスチャンは、二つの伝統の中に生きています。一つは、ヘブル人への手紙で語っているイスラエル、またキリスト教の伝統です。そしてもう一つは、日本人としての伝統です。それら二つの伝統はともに、私たちを抜きに全うされることはありません。
この聖句の中に「さらにすぐれたもの」とありますが、これはキリストを表しています。まことの羊飼いなるキリストです。キリストによって、イスラエルまたキリスト教の伝統は完成するのです。キリストによって、日本の伝統も完成するのです。
私たちがキリストを知ったのは、これらの伝統を全うしていくためです。雲のようにおおって私たちを見守ってくれている先人たちの期待に答えて、この日本で神様のご栄光を現わしていくことなのです。だから一二章二節に、
「信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスは、ご自分の前に置かれた喜びのゆえに、はずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました」
と書かれています。イエス様から目を離さないでいなさいと。イエス様はその雲の真ん中で、あなたを見つめていらっしゃいます。あなたのすぐ近くにおられるのです。
私はそれを思うと、非常に敬虔な思いになります。目で見えるものがすべてではありません。目に見えない世界にこそ、真実なものがあります。この日本でも、日本のキリスト教を推し進めてきたたくさんのクリスチャンの先輩たちの働きがありました。私たちはそれを受け継ぎ、また大きくしていくことが大切です。イエス様にあって、それをしていく。
日本のことを思い、あの残酷きわまりない世界の中で生き抜いて、この日本という国を私たちのために残してくれたたくさんの先人たちがいます。彼らは雲のように私たちを取り巻いてくれています。
その彼らの思いも受け継ぎ、発展させていきたいと思うのです。
クリスチャンになった真珠湾攻撃隊長
先ほど真珠湾攻撃のことをお話ししましたが、真珠湾攻撃の飛行隊の隊長は、渕田美津雄・海軍中佐というかたでした。彼は零戦に乗って、真珠湾攻撃に参加し、指揮したのです。「トラ・トラ・トラ」(我、奇襲に成功せり)の電文を打ったかたです。
淵田中佐は戦後、クリスチャンになりました。さらに伝道者になりました。彼は戦後七年目にアメリカに渡ったとき、爆弾ではなくて聖書を持っていきました。

真珠湾攻撃の隊長は、のちにキリスト教伝道師
になり、アメリカでキリストの愛と福音を伝えた
彼はキリスト教の伝道師として、アメリカ中を旅して、キリストの愛と福音を宣べ伝えました。ときには、真珠湾攻撃のリーダーという事で、嫌な思いもしたようですが、圧倒的に彼を励ますアメリカ国民の方が多かったそうです。
淵田さんの回心のきっかけの一つに、アメリカのディシェーザー宣教師との出会いがありました。ディシェーザー宣教師自身、かつては戦時中に日本本土を爆撃した、アメリカ軍の飛行隊員だったのです。彼の飛行機は、あるとき燃料切れで日本軍制圧下の中国に不時着しました。彼は捕虜となり、日本で捕虜として生活するなか聖書を読んで救われたのです。
淵田さんとディシェーザーさんは、かつては敵同士だった。しかし、神様の不思議な導きによって二人ともクリスチャンとなりました。そして共に伝道者として神様の愛を伝えるようになった。彼らは一緒に組んで伝道してまわったのです。敵・味方を乗り越えるもの、それはイエス・キリストです。憎しみを乗り越えるもの、それはイエス・キリストです。
「キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ちこわし、ご自分の肉において、敵意を廃棄された方です」(エペ二・一四〜一五)。
また、淵田さん愛用の聖書の裏表紙には、イエス様が十字架上で言われた言葉が書かれています。
「父よ、彼らをおゆるしください。彼らは何をしているのかわからずにいるのです」。
これは、淵田さんが回心するきっかけとなった聖句でもありました。
淵田さんは、すでに天国に帰りました。私たちの先輩として、雲のように私たちを取り巻いてくれています。彼ら先輩たちのしたことも、私たちを抜きに全うされることはないのです。私たちはバトンを渡されています。私たちも、ゴールを目指して走り続けなければなりません。そして次のランナーに、無事バトンを渡さなければなりません。
ゴールには、イエス様が待っておられます。
「信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい」。
また、
「このように多くの証人たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも、いっさいの重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競走を忍耐をもって走り続けようではありませんか」
と書かれています。私たちも、イエス様から目を離さず、信仰のゴールを目指して走り抜きましょう。
久保有政著
|

 メッセージ(日本)
メッセージ(日本)