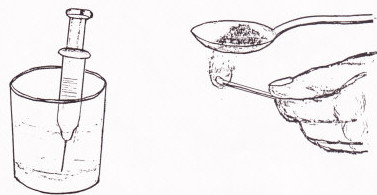無神論の結末
「人生は無意味だ」「世界はばかげている」の結末

反対者に対する粛正、民衆への抑圧・・・。
無神論は、古代ギリシャの昔から、しばしば思想家たちの間に見られるものでした。しかし現代における無神論は、その影響を与える範囲の広さにおいて、過去のものとは比べものになりません。
近代から現代にかけて、無神論は強固な哲学的・論理的基盤を持つようになりました。
そしてそれは、もはや一部の哲学者の間だけでなく、一般大衆の知性と心情に浸透し、今や大人から子供に至るまで、世界中の多くの人々の世界観や人生観を形成してきたのです。
人が無神論をとるか、あるいは創造者なる神を信じるかという問題は、その人の世界観・人生観に関わる重要な問題であり、ゆくゆくはその人の人生を大きく左右します。
無神論は、現代人に何を与えたでしょうか。それは人々の考えをどのように左右し、どのように決定づけてきたでしょうか。人生・文化・社会の上に与えた無神論の影響と、その結末を、考察してみましょう。
進化論と無神論
一九世紀に、チャールズ・ダーウィン(一八〇九〜一八八二年)は『種の起源』を著し、彼の「進化論」を公表しました。しかし彼は、その進化論が、後の時代の無神論思想をこれほどまでに増長させることになるとは、思いもよらなかったようです。
ダーウィン自身は、決して無神論を助長させるために、進化論を主張したわけではありませんでした。ダーウィンは、「種の起源」初版の巻末に、命は最初、
「創造者によって、二、三の、あるいは一つの形態に吹き込まれた」
に違いないと書きました。彼は、聖書的な有神論者だったわけではありませんが、「進化」全体をつかさどっているのは神であると考え、少なくとも神の存在を信じていたのです。
しかしこの本は、世界に異常な反響を巻き起こしました。ドイツ唯物論者をはじめ、イギリスの生理学者で進化論推進者となったハクスレーなどから、熱狂的に歓迎されました。
そのため成功に酔ったダーウィンは、急きょ第二版から「神」を削除してしまったのです。
こうして、「進化」をつかさどるのは「神」ではなく、「偶然」になってしまいました。無神論者が欲しかったのは、「神」ではなく、神ぬきに生命と自然界の起源を説明することだったのです。
以後、進化論は無神論の理論的基盤の座に据えられ、無神論者の手によって熱心に推進されました。
共産主義を説いたドイツのカール・マルクス(一八一八〜一八八三年)は、『種の起源』を読んで、これは「神に致命的な打撃を与えるものだ」と言って狂喜した、と言われています。
進化論は、実験や観測によって実証することのできない"仮説"であり、化石記録や生物の多様性に対する一つの"解釈"に過ぎません。少なくとも生物学者たちは、そのことを知っていました。
しかし、それが一般大衆に話される段になると、「進化は疑うことのできない事実である」と吹き込まれました。たとえば、著名な進化論者ジュリアン・ハックスリは、多くの聴衆を前に、
「我々すべては進化の事実を受け入れる。・・・・生命の進化は・・・・事実であり、我々の全思考の根底である」
と語りました。
進化の最も強力な「証拠」とされたのは化石ですが、実際には、本誌において幾度となく解説してきたように、化石は今日では進化の証拠ではなくなっています。
膨大な量に及ぶ掘り出された化石は、進化を証拠づけているどころか、進化を否定しているのです。
その辺の事情は、最近日本でもベストセラーとなった「エントロピーの法則」(ジェレミー・リフキン著 祥伝社)の第二巻の中でも紹介されています。
しかし、特に無神論的土壌の強い日本では、依然として、教科書にしても、生物学の解説書にしても、進化論一色です。
アメリカなどでは、最近進化論の間違いを認める科学者や知識人が増えていますが、日本ではまだ、進化論に反対するだけの勇気をもった科学者は多くありません。
かつては、進化論が無神論を助長した時がありましたが、今では無神論が進化論を保守しているのです。
進化論と社会主義
進化論の影響は、単に生物学の分野にとどまらず、広く社会の諸思想に多大な影響を残しました。たとえばマルクスは、
「ダーウィンの著書は非常に重要であり、歴史における階級闘争の根拠となる」
と語り、進化論的な考えを、社会主義・共産主義の理念にまで適用しました。
ダーウィンは「適者生存」、すなわち、外界の状態に適する性能を備えるものは生存して繁栄し、そうでないものは自ら衰亡して絶滅に至るという考えを説き、「自然淘汰」説を唱えました。
社会主義者らは、こうした考えを階級闘争の根拠に据え、彼らの社会主義革命をすすめるための力としたのです。
このことを伝え聞いたダーウィンは、驚いて、シェルゼル男爵あての手紙にこう書いています。
「自然淘汰の考えをもとにして、社会主義と進化論との関係が取り沙汰されているとのことであるが、ドイツでは随分ばかげた考えが流行しているものだ」。
そしてこの手紙を書いた翌年に、マルクスから『資本論』の英語版を献呈したいとの申し出を受けた時には、ダーウィンは「さぞ驚いたであろう」と、ダーウィン伝を書いたデ・ビーアは述べています。
さて進化論によれば、人間は無生物の状態から偶然的な変化の積み重ねによって生じてきたわけです。
もし、この考えを徹底すれば、人間が今存在していることに、何かの目的や意味を見いだすことはできません。
マルクスや、彼の協力者エンゲルス(一八二〇〜一八九五年)の唱えた「唯物論」にしても、それは同様です。唯物論によれば、あらゆるものの根源は物質であり、「精神は物質が生んだ(最高の)産物」としてしか見られません。
ですから、精神は物質に対して独立した価値を持つものとは見なされず、人間の中に変わらずに存在する本質や実体というものも認められていません。
実際マルクスは、『資本論』の中で、人間の本質は「社会全体の調和」以外の何物でもない、と述べています。
自分の育った環境や社会的パターンの所産にすぎない、あるいは社会の一分子にすぎない、とされているわけです。
このように唯物論は、人間の尊厳や価値に関する理論的基盤を、なんら持ち合わせていません。
ただ、共産主義がそれほど勢力を持っていないところで、人間の尊厳や権利に関する議論が人を引きつけている、ということはあります。
しかし、ひとたび勢力を持つと、大多数の欲求という考え方が尊厳や権利にとって代わり、「革命」という大義が、いかなる無情な手段をも正当化します。
そのために、反対者に対する恐ろしい粛正や、虐殺、民衆への抑圧といった行為が、当然のように行なわれてきました。
旧ソ連でスターリン(一八七九〜一九五三年)が、反対派に対して大粛正を断行したことや、中国の文化大革命で多くの反対者が殺されたことなども、そうした主義により、当然起こるべくして起こった行き過ぎであったと言えるでしょう。
旧ソ連から亡命したソルジェニーツィンは、その著『収容所群島』第二巻の中で、ロシア革命から一九五九年までの間に、獄中でのべ六六〇〇万人に及ぶ人々が死んだと見積もっています。
「強者の論理」が唱えられる
イギリスの哲学者ハーバート・スペンサー(一八二〇〜一九〇三年)も、進化の理論を社会や人生の問題に拡張し、大衆化した人のひとりでした。
彼は、生物学的進化の理論を倫理を含む全人生の問題に拡張し、実際に「適者生存」という言葉を造り出しました。彼は言いました。
「能力のない者の貧困、怠惰な者の飢餓等、これら弱者の生み出すものを強者の論理によって肩代わりさせること、それは大きな先見の明のある博愛であり天命である」。
強者のみが生き残るべきであるとするこの考えは、後になってもっと行き過ぎました。
ナチスの総統アドルフ・ヒトラー(一八八九〜一九四五年)は何度も、キリスト教とその愛の考え方は"強者の弱者に対する倫理"によって置き換えられるべきである、と語りました。

アドルフ・ヒトラー。彼は何度も、
キリスト教とその愛の考え方は、
「強者の弱者に対する倫理」によって
置き換えられるべきであると語った。
また、ナチスのゲシュタポ(秘密警察)のリーダーであったハインリッヒ・ヒムラーも、自然法則は「適者生存」という当然の方向を取らねばならない、と述べています。
その結果は、他国への容赦ない侵略や、六〇〇万人に及んだユダヤ人の虐殺でした。
ドイツ民族の卓越性をもって世界を制覇しようとしていたナチスは、自分たちこそ世界を引き継ぐ真の「適者」であるとし、その「強者の論理」を、他国やユダヤ人に対して強要したのです。

600万人に及んだユダヤ人の虐殺。
ゆがんだ道徳基準
このように無神論に基づく思想は、単に一個人の思想にとどまらず、社会や歴史の上に大きな影響を与えてきました。神の否定は、道徳の基準を取り去り、価値観をゆがめ、時に人々を盲信的にしてきたのです。
フランスの小説家マルキ・ド・サド(一七四〇〜一八一四年)の場合も、そのことは異常なまでに現れています。二〇世紀の好色文学者たちは、好色文学の起源を彼までさかのぼらせますが、彼は"化学的決定論者"でした。
彼は、"人間の精神は、脳内の化学反応によって決定されている。だから、道徳に意味はない"と考える人のひとりだったのです。
人間が何を考えるか、何を思うかということは、脳の中の物質の化学反応によって決定されている。人間がそのように決定された存在なら、道徳に意味はない。彼はそう考えました。
そのため彼においては、本能の命じることはすべて正当化されました。その結果は、サディズム、すなわち加虐淫乱症と呼ばれる特に女性への虐待でした(サディズムという語は、サドの名から来ている)。彼は書いています。
「自然は、我々(男性)を最も強い者としたから、我々は彼女(女性)に対して何でも望むことをしてよい」。
このように、神を否定したところには、「人間は決定されたもので、その存在に意味はない。道徳はナンセンスだ。本能の命じることを行え」という考えが残るのみだったのです。
「人間は無意味だ」
化学的決定論や、進化論に毒された多くの人々が、人間の存在に意味を感じられなくなったのは、当然のことでした。それらの理論は、人間の尊厳や価値、あるいは目的や意味について、何の根拠も与えないからです。
それらの理論が示しているのは、単に人間が目的のない宇宙の一部であり、人生に価値や意味を求めることはできない、ということだけです。
こうした無神論の思想が最終的に行き着くところを、私たちはドイツの思想家フリードリッヒ・ニーチェ(一八四四〜一九〇〇年)の思想や生涯に見ることができます。
彼はその著作の中で、初めて現代的な無神論の表現として、「神は死んだ」と言いました。これは、神を信仰する時代は終わった、あるいは、「神」はもはや無意味な存在だ、という意味です。
ニーチェは、なぜこう言ったのでしょうか。
近代社会が生んだ様々な観念や思想は、人間の無意味さをますます顕著なものとしていました。人間の存在の意味は、以前は神によって与えられていたものです。
しかし、神はいない。かつては神によってしか意味が与えられなかったものも、今はみな空虚だ。
彼はそう感じました。神の時代は終わった。神は死んだのだ。だから、神を信じることをやめて、無意味と虚無の現実を直視せよ。
そして、在来の価値観をすべて捨てて、新しい価値を創造すべく、「超人」(虚無に耐え、新しい価値を創造していく人間)への道を歩め。そう彼は説いたのです。
しかし彼自身も、その虚無には耐えられなかったようです。彼は一八八九年に発狂しましたが、それは無意味さと虚無に捉えられた精神が、当然のように呼び起こした悲劇でした。人間の意味を神以外のところに求めることは、不可能なのです。
ニーチェの思想は、のちにナチスの青年たちの指導原理の一つとされました。また、かつて自衛隊に乱入して割腹自殺を遂げた三島由紀夫なども、ニーチェの愛読者でした。

フリードリッヒ・ニーチェ。彼は45歳の時に発狂した。
「世界はばかげている」
無神論思想が行き着くところは、結局"人間は無意味である"そして"世界はばかげている"という考え以外にはありません。
それは、フランスの思想家ジャン・ポール・サルトル(一九〇五〜一九八〇)の場合も、そうでした。
サルトルによれば、この世界は「嘔吐」、すなわち吐き気をもよおさせるような"ばかげた世界"です。あらゆるものが、無意味の中で存在している。
しかし人間は、無意味に生きることには耐えられません。人間はどうしても、自ら自分の存在の意味を確証しなければならない。人間には、生きていることの実感を与えてくれるような何かが必要です。
彼は、それは傍観者としての立場を捨てて、この「目的のない世界」の中で、自ら意志的に行動していくことだ、と説きました。そして、そのとき自分の存在の意味を確証できると。
ドイツの哲学者マルティン・ハイデッガー(一八八九〜一九七六年)も、基本的には同じ考え方をしましたが、彼は現代人を特徴づけるものとして「不安」(漠然としたおののき)を語ります。
「不安」は、「恐れ」とは違って、はっきりした対象をもちません。たとえば、私たちが将来について「不安」だと言うとき、それは"将来に何があるかわからないから不安"なのです。
ハイデッガーはこの「不安」が、人々に自分の存在の確かさを与える、としました。そして、そこから人生の意味も出てくると。
しかし彼は、老年になってこの考えを捨てました。「不安」というような漠然とした感情では、やはり人生に確かな指針を与えることはできないのです。
カール・ヤスパース(一八八三〜一九六九年)の場合は、人生の無意味を解決するものとして、「究極経験」(最終経験)と呼ぶものについて語りました。
たとえ私たちの精神が「人生はばかげている」と言おうとも、私たちは、人生に意味があると信じ込めるような巨大な経験をもつことができる、と彼は主張しました。
つまり、大きな感動を伴う何かの体験をすることによって、人生に意味があると信じ込むことも可能だと言うのです。その経験を、彼は「究極経験」と呼びました。
しかし、もとよりこのような捨てばちの試みが、望むような良い結果をもたらすはずはありません。
英国の思想家オルダス・ハックスレー(一八九四〜一九六三年)は、この考えを受け継いだ一人でしたが、彼はその「究極経験」を与えるものとして、「麻薬」を主張しました。
彼は、健康な人に麻薬を与えれば、彼ら自身の頭の中に真理を見い出すことができる、と言いました。そうすれば、望む時にいつでも究極の体験をすることができると。
彼は、この考えをその著「すばらしい新世界」(一九三二年)の中で示唆し、死に至るまでこの考えに固執していました。
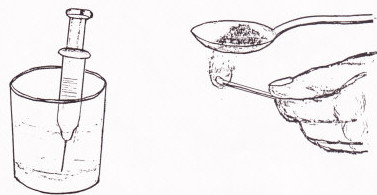
少なからぬ人々が、麻薬によって"究極の経験"
をすることができると、主張するようになった。
無神論は至る所に
私たちにとって恐ろしいことは、以上述べてきたような哲学者たちの無神論が、単に哲学者の間の難しい論議にとどまらず、ひじょうに大衆的な方法で広まっているということです。
たとえば、ニーチェの著した『ツァラトゥストラはかく語りき』は、彼の無神論思想を詩のかたちに表現したものです。
また、サルトルの『嘔吐』、カミュの『異邦人』『ペスト』、ボーヴォワールの『招かれた女』などは、小説形式で書かれた哲学的著作です。これらはまた、演劇としても上演されました。
このように、今や無神論思想は、難しい哲学の専門用語を使わずとも、ひじょうに大衆的な手段で、人々の目にふれ、耳に入っています。
そのほか、音楽、美術、映画など、あらゆる文化を通して、無神論は人々の知性と心情に、いまや深く浸透しています。
たとえば、交響楽団の指揮者レナード・バーンスタインは、グスタフ・マーラー(一八六〇〜一九一一年)の音楽について、人間や世界の意味についての究極的あいまいさが、彼の第九交響曲のフィナーレに聞かれると述べています。
そして我々の世紀(二〇世紀)は死の世紀であり、マーラーはその音楽的予言者であるとも述べています。
また、一九六三年に映画「沈黙」の監督をしたイングマール・ベルイマンは、その際のインタビューで、「神は死んだ」と結論するに至ったと語りました。それゆえ、宇宙の中には「沈黙」があるのみだと。
これほどに、世界に無神論思想が蔓延していると、その犠牲者となる人々は少なくありません。
数々のベストセラーを書いた文学者アーネスト・ヘミングウェイ(一八九九〜一九六一年)も、後期は厭世主義にとりつかれていました。「すべては無だ。人間も無だ。それだけのことだ」と彼は言いました。
筆一本でベストセラーを書いて、富を獲得、そのお金で酒と性的行為にふけっては、空しさをまぎらわす。その繰り返しの末、彼はついに自殺しました。
また、日本の文学者の中に自殺者が圧倒的に多いという事実も、無神論思想の蔓延と無縁ではないのかも知れません。
無神論思想の「人間は無意味だ」「世界はばかげている」などの考えに、足もとを掬われた人が多くいました。
無神論思想は、今やひじょうに大衆的です。ある女子高校生が自殺したとき、彼女は「われら不条理の子」という本を携帯していました。
そして、その本の中には「真理は主観的なものである」という言葉があり、それには赤でサイドラインが引かれていました。
今日、日本では様々な新興宗教が現われてきており、「宗教ブーム」とも呼ばれることがあります。これは、無神論思想が弱体化したことを意味するのでしょうか。
そうではありません。無神論は、あらたな衣を帯びて、この日本にはびこっているのです。
戦後最大の犯罪を犯したと言われるオウム真理教の教祖・麻原彰晃被告は、自分を「神」と言っていました。
彼は"有神論者"だからこう言ったのでしょうか。そうではありません。彼はこう言うことによって、自分が真の神の存在を否定する無神論者であることを、示しているのです。
本当の神の存在を知っていれば、あのように恐ろしい犯罪を犯すことは誰にもできません。神を否定する者だからこそ、あのように恐ろしいことができたのです。
本当の神を知らないことは、人生最大の不幸です。それによって、人生のすべてが誤った方向に行ってしまうからです。
最近、朝日新聞の相談室の欄で、ある人気俳優が、悩みある主婦の質問に答えていました。
「いつも夫婦の間で問題になることは、生きる理由がわからないということ。子どもが生まれてきたとき、そのことを聞かれたら何と答えよう。子どもをつくる理由もわからない」。
この質問に、回答者は何と答えていたでしょう。「正解がないのが人生」。それが答えでした。神なき人生観からは、このような答えしか返ってきません。
人生は、はたしてそのようなものなのでしょうか。人間が生きる意味に関して、本当に満足できる答えを、私たちは見つけることはできないのでしょうか。
神はおられる
「人生は無意味だ」「世界はばかげている」という考えになってしまうのは、そもそもその考えの出発点となったものが間違っているからです。無神論からは、何ら良いものは出てきません。
神はおられます。神の存在を信じることは本来、子が父を信じるのと同じように自然なことです。そして天地万物を造られた神を信じ、神と共に生き始めるならば、人生の意味や目的は自然に開かれてきます。
人生の目的を知って生きるのと、そうでないのとでは、雲泥の差、または天と地ほどの開きがあります。
創造者を知ることなしに生を知ることなく、天の父を知ることなしに人生の平安を得ることはありません。
神はあなたを愛しておられます。
「神は、じつにそのひとり子(キリスト)をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを得るためである」(ヨハ三・一六)。
神の愛の中にいない人は、誰一人いません。神はすべての人が真理を知り、幸福な人生を送ることを願っておられます。
しかし、神がお与えになる幸福を享受するのを妨げているものがあります。それは神を否定する心です。神を認めない心こそ、じつは人間最大の罪なのです。
神の存在は、天地万物・大自然の中に、明らかに示されています(ロマ一・二〇)。また、私たちの心に「良心」という人生の掟を書き記したかたは、神ご自身です。そして神を求めるなら、神を見いだせるようにして下さったのです。

神の存在を認めることなしには、
大自然の意味を知ることも、
人生の意味を知ることもあり得ない。
神の存在については、神からの啓示の書物である『聖書』が、あなたに詳しく示してくれることでしょう。
あなたは聖書を学び、その教えを実践していくことによって、必ずや神の存在とその愛を、人生で体験し、真の幸福を確立していくことができるのです。
[参考図書]
『それでは如何に生きるべきか』(フランシス・A・シェーファー著)いのちのことば社発行
久保有政著(レムナント1995年11月号より)
|

 神
神