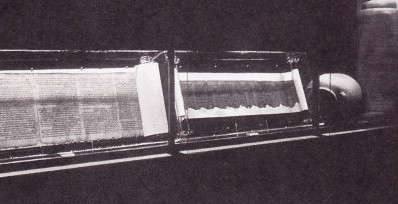わかる組織神学 神論
神の存在証明・ご性質・神の御名

因果律により、結果は原因を越えるものにはならない。
創造者なる神は、宇宙自然以上のおかたである。 セガンティーニ「春の牧場」
人生の目的は、神と共に生きる幸福にある。それは神の存在を知ることに始まる。
一 神の存在証明
神は実在である。神の存在は、おもに次の五つのものがあかししている(示している)。
(1) 宇宙自然
宇宙自然は、永遠に生きておられる神の創造の力と、神性、また神の存在をあかししている。聖書は言っている。
「神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこのかた、被造物(造られた物)によって知られ、はっきりと認められるのであって、(神の存在について)彼らに弁解の余地はない」(ロマ一・二〇)。
芸術家の感性は作品に現われる。建築家の知性は建造物によって知られる。同様に、神の永遠の力と神性は、被造物である天地万物、宇宙自然にあらわれている。
花が美しいのは、創造者なる神の感性の現われである。夜空の星が悠遠なのは、神の偉大な創造の力の現われである。
宇宙を支配する物理的化学的諸法則が美しい秩序に満ちているのは、神の理性の現われである。宇宙を研究し、自然を研究する科学者は、宇宙がきわめてよく出来ていることに驚きの声をあげている。
あなたの目の前にもし時計があれば、それを作った人がいるはずである。あなたの目の前に自動車があれば、それを作った人がいるはずである。
それらを作るために、どれだけ多くの人々の知性と努力、また研究がなされてきたか知れない。
同様に、私たちの前に広がる荘厳な宇宙、美しい大自然の背後にも、知性を有する偉大な創造者がおられるのである。
これには、さらに宇宙の法則の存在を思うとよい。宇宙には、様々の物理的化学的法則が存在している。
「重力の法則」「質量とエネルギーの保存の法則」「エントロピーの法則」、そのほか惑星の運行に関する法則や、電磁場を支配する法則、相対性理論や量子力学に見られるような法則等もある。
これらは、宇宙創生の時から、変わらずに全宇宙空間を支配してきた。過去・現在・未来にかけて、これらの法則は進化も退化もせず、不変のものとして支配している。
こうした不変のものが、一体どうやって生まれたのだろうか。もしこれらの法則が一つでも欠ければ、宇宙は現在のような宇宙ではなくなるのである。そして、おそらく生命は存在せず、人間も存在しなかったであろう。
宇宙は、驚くほどよく出来ている。それは偉大な知性によって計画され、デザインされたものなのである。こうしたものを造ったかたを、私たちは「神」と呼ぶ。
また私たちは、「因果律」というものを知っている。因果律は、宇宙全体を支配している。この法則は一般に、
"物事の変化生滅の根本には、必ず原因と結果の関連がある"
また"同一の原因があれば同一の結果が生じる"ことをいう。
したがって、宇宙が存在し、また様々な物理的科学的法則が存在することは、その背景にそれらを存在するに至らせた原因がある、ということである。その原因を、私たちは「第一原因」と呼ぶ。この宇宙の第一原因こそ、神ご自身なのである。
因果律はまた、物事の因果に関して、
"結果は、質においても量においても原因を越えるものにはならない"
と主張する。たとえば、人間が時計を発明する。このとき、人間と時計のどちらが優れているかと言えば、それは時計を造った人間なのである。
同様に、広大無辺のこの宇宙を造ったかたは、宇宙以上のおかたである。神は空間に対しては無限、時間に対しては永遠、能力に関しては全知全能のおかたである。また神は、この宇宙に存在する人間以上に優れた、偉大な知情意を有する方なのである。
(2) 生命
この宇宙には生命が存在する。生命は、宇宙の中で最も神秘的なものである。
人は生命をつくり出すことができない。人がたとえ、細胞の構造や遺伝子DNAの構造等に関して知識を深めても、それで生命の神秘そのものを解明したわけではない。それは単に物質レベルの研究で解明できるものではない。
春に一斉に芽を出す植物たちの生命力は、いったいどこから来るのか。大地の上に、また海の中に住む各種の動物たちの生命は、いったいどこから来たのか。また、私たち人間の生命が、この宇宙に存在し、また保たれているのは何故か。
生命は決して偶然の産物ではない。それは生命なる神が、この宇宙にお与えになったものである。
「いのちの泉はあなた(神)にあります」(詩篇三六・九)。
「すべての生き物の命と、すべての人間の息とは、その御手のうちにある」(ヨブ一二・一〇)。
因果律により、神は宇宙に存在するすべての生命よりも、大いなる生命であられる。

人が生命をつくり出すことはできない。
生命は神からのものである。
(3) 聖書
神からの啓示の書物『聖書』は、神の存在を証明する。
聖書は地球が何もない空間に掛けられていることを知っていた。
現代人の私たちは、地球が宇宙空間に浮いており、地球が何か目に見えるもので支えられているのでないことを知っている。
しかし聖書はこのことを、今から約三千年も前に、はっきり記していた。聖書・ヨブ記二六章七節に、こう記されている。
「神は・・・・地を何もない所に掛けられる」。
これが記された三千年前は、人工衛星から人が地球を眺めることはもちろんできなかったし、人々の地理上の知識もほとんどない時代だった。
また古代人はみな、地面の下には何か地面を支えている物体が何かある、という考えを持っていた。しかしその古代世界において、すでに聖書は、地球が何もない空虚な空間に掛けられていると明確に述べていたのである。
これは神が存在し、神からの霊感を受けて聖書が書かれたからである。
聖書は地球が球形であることを知っていた。
聖書はまた、今から約二七〇〇年も前に、地球が丸いものだと述べていた。
「主(神)は地球のはるか上に座して・・・・」(イザ四〇・二二口語訳)。
この「地球」と訳された言葉は、原語では「地の円」である。「円」とは水平線の形を言っている。丸い水平線である。
「神は・・・・(地球創造の時)水の面に円を描いて、光とやみとの境とされた」(ヨブ二六・一〇)。
水平線より上に太陽が来れば昼となり、下に来れば夜となる。水平線は「光とやみとの境」である。これが円形になるように、神は地球を造られた。
しかしこの「円」は、二次元的な"丸い平たいもの"の意味ではない。聖書はむしろ、地が球形であると示唆している。
「そのとき(地球創造の時)、わたし(神)は雲をその着物とし、黒雲をそのむつきとした」(ヨブ三八・九)。
「むつき」は、赤ん坊をグルグル巻きにして包む細長い布で、産着である。神は地球を創造されたとき、黒雲を、誕生したばかりの地球のむつきとされた、というのである。そうであれば、地球は立体的でなければならない。
このように聖書は、地球が三次元的に丸いもの、すなわち球形だと述べていたのである。
古代人は一般に、地球は平べったいものとしか考えていなかった。しかし、約三千年も前に聖書がこのように述べることができたのは、神が存在し、聖書が神の霊感を受けて書かれたからなのである。
聖書の予言は神の予知に基づく
神の啓示の書物『聖書』には、多くの予言(預言)が記されているが、これも私たちに神の存在を知らせている。
聖書の予言は、じつに驚くべきものであり、それらはことごとく実現成就している。
イスラエル民族の歴史に関する予言も、その一つである。
イスラエル民族がエジプトで約四〇〇年のあいだ奴隷になること(創世一五・一三)、そのあと多くの金銀をたずさえて脱出しカナンの地に戻ってくること(創世一五・一四)、そののち大王国を形成すること(申命二八・一〜二、創世一五・一八)、しかし堕落して神の審判を受けバビロン帝国の捕囚となること(申命一八・四九、イザ三九・六)、またそののち一時回復するが全世界へ離散すること(申命二八・六四〜六五)――これらのことはすべて、出来事が起きるずっと前に聖書の中に予言され、すべてその通り成就した。
さらに、予言は二〇世紀にも及ぶ。イスラエル民族(ユダヤ民族)は約一九〇〇年間にわたって全世界に離散していたが、一九世紀後半から次第にパレスチナに帰り始め、ついに一九四八年にイスラエル共和国を建国した。これは、その二六〇〇年も前に聖書の中で予言されていたことの成就なのである(エゼ三六・二四、イザ一一・一二)。
そのほか聖書は、古代世界に栄華を誇ったバビロン帝国(新バビロニア帝国)の滅亡と永遠の廃虚化(イザ一三・一〜二二)、繁栄した都市国家ツロの没落(エゼ二六・三〜一四)、ペルシャ帝国や、ギリシャ帝国、ローマ帝国の出現(ダニ二・三九〜四二、五・二八、八・二一)、キリストがローマ帝国の時代に降誕されること(ダニ二・三四〜三五)、さらに現代の欧米諸国の繁栄(創世九・二七)、等も予言し、すべて成就している。
聖書は、キリストのご生涯についても多くのことを予言していた。キリストが降誕される時期(ダニ九・二五)、場所(ミカ五・二)、家系(創世四九・一〇、詩篇八九・二九)、生涯の特長(イザ五二・一三〜一五)、違法な裁判にかけられること(イザ五三・八)、十字架にかけられること(マタ二〇・一九)、十字架死の意味(イザ五三・一〜六)、骨は砕かれないこと(詩篇三四・二〇)、やりで突かれること(ゼカ一二・一〇)、復活(イザ五三・一〇)、そのほか多くを予言し、すべて成就したのである。
聖書は、二〇世紀以降に世界に起こるはずの事柄についても、多くを予言している。これらはすでに成就し始めていると、多くのクリスチャンは感じている。
聖書の予言は、神の予知に基づくものであって、その正確さと内容の深さは他に例を見ない。これは、神の存在をあかしする一つの例である。
そのほか
聖書の予言以外にも、聖書には「予型」というものがあり、これも神の存在とそのご計画を私たちに知らせている。予言が、言葉によって未来のことを示すものであるのに対し、「予型」は、出来事や人物等によって未来のことを示すものである。
聖書をよく調べていくと、私たちは、それが人知をはるかに越えたものによって記されたものだという、実感を持たざるを得なくなってくる。読者は本書を読みながら、きっとそのことを思うようになるであろう。
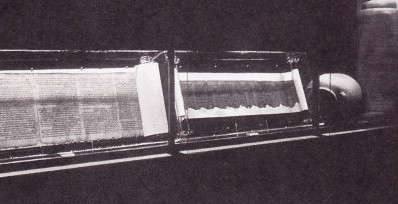
『聖書』――それは神からの啓示の書物である(死海写本)。
(4) 人間の宗教心
つぎに、人間にある宗教心も、神の存在をあかししている。
世界中どこの国でも、必ず宗教というものが見られる。宗教を禁じた共産圏でさえ宗教は盛んだし、科学や文明の発達した先進国でも宗教を持つ人が必ず多くいる。
宗教はどんなに文明が発達しても、なくなることは決してない。宗教心は、どんな人も多少なりとも持っている。
「私は無宗教だ」という人も、人生に行き詰まったり大病をすれば、神に祈ったり、突然目覚めて信仰に入ったりする。宗教心は、潜在的に、本能のようにあらゆる人間の中に宿っているのである。
本能には、必ず対象がある。赤ん坊は本能的に乳を欲しがる。そこには母親の乳という対象が存在している。
食欲には食物という対象があり、性欲には異性という対象が存在する。草が上に伸びる。そこには太陽の光という対象が存在しているからである。
同様に、あらゆる人間に多少なりとも宗教心が、一種の本能のように存在するという事実は、そこに対象として神が存在しているからにほかならない。
神は人の心に、一つの空洞を設けられた。その空洞は、神ご自身によってしか埋められない形と大きさをしている。その空洞のために、人は神を求める。聖書は言っている。
「神は・・・・人の心に永遠への思いを与えられた」(伝道三・一一)。
人には誰でも、潜在的に「永遠への思い」、すなわち永遠的真理や、愛、また永遠の神を求める心が与えられているのである。この宗教的本能の存在は、対象としての神の存在をあかしする。
「宗教」という言葉は"本もとの教え"――人生で最も大切な教えという意味である。しかし、「宗教」と呼ばれるすべての教えが、真の神知識を持っているわけではない。
宗教には"人からの宗教"と"神からの宗教"がある。世には、人からの宗教――人が始めた宗教がたくさんある。しかし、これらはみな不完全なものである。先の聖書の言葉は、次のように続いている。
「しかし、人は、神が行なわれるみわざを、初めから終わりまで見きわめることができない」(同三・一一)。
人の悟性、理性、知性等に基づく宗教は、真の神知識を持っておらず、不完全である。真の神知識が得られるのは、"神からの宗教"――神ご自身が啓示された宗教のみである。それがキリスト教なのである。

宗教心は、神から与えられた「永遠への思い」の基づく
(林 竹次郎画 「朝の祈り」)。
(5) 私たちの体験
神の存在は、私たちの人生において体験できる。
「静まって、わたしこそ神であることを知れ」(詩篇四六・一〇)。
神は私たちの目には見えないが、私たちを愛し、私たちの人生に対して深い関心を持っておられる。神は私たちの祈りを聞き、真摯に求める者に対してご自身を現わして下さる。
クリスチャンはみな、人生において神を体験してきた人々である。神の存在は、単に頭で考えて知ることのできるものではない。それは人生で体験して初めて、明確にわかるものである。
神の存在を知る最も良い方法は、真摯に求めることである。また祈りである。神はどんな祈りも、決して無駄にはなさらない。神は私たちの真摯な心の叫びを、耳を澄まして聞かれる。そして、何らかの方法で答えてくださる。
二 神に関する基本的知識
真の神は、どのようなかただろうか。
(1) 唯一にして絶対
唯一
「われわれの神、主は唯一の主である」(申命六・四)。
神は唯一であって、ほかに神は存在しない。多神教は、宗教の堕落した形態である。
ある人々は、多神教が発達してやがて「拝一神教」(ゾロアスター教のように、多くの神々のうち一つの神だけを拝する宗教)が生まれ、また唯一神を信じる「唯一神教」が生まれたと主張してきた。しかしこれは、最近の考古学の発達によって、事実は逆だったことがわかっている。
多くの考古学的資料は、人間は原始の時代には唯一の神を拝していたが、やがて急速に多神教に堕落していったことを示しているのである。そののち、唯物論や無神論が生まれた。
多神教の中に、真の神知識は存在しない。真理が一つであるように、神は唯一である。
絶対
唯一の神のご意志は、絶対である。「絶対」とは文字通り"対立を絶する"ということである。
神の前に対等に立てる者は、誰もいない。どんな人間も、どんな被造物も、神と対等ではない。神の意志が、宇宙の意志である。
「わたしは(神)は、わたしの望む事をみな成し遂げる」(イザ四四・二八)。
また、神のご判断は絶対である。神が裁きをされるとき、それは唯一の正統なものである。人間に対する真実な裁判ができるのは、最終的に神のほかにおられない。絶対的な主権は神にある。
絶対者を絶対者として認め、おそれかしこむところに、信仰が始まる。
(2) 無限であり遍在される
無限性
神は無限であって、空間の大きさや広さに限定されない。むしろ空間を超越しておられる。かつてイスラエルのソロモン王は、神殿を建設したときに祈って言った。
「それにしても、神ははたして地の上に住まわれるでしょうか。じつに天も、天の天も、あなたをお入れすることはできません。まして、私の建てたこの宮など、なおさらのことです」(一列王八・二七)。
ソロモンは神殿を、神の住まいとして建てたのではなく、民の祈りの家として建てたのである。
神は、天地宇宙の大きさ、広さを超えて、無限であられる。神を限定することは、誰にもできない。神は超越者であられる。

ソロモンは神殿を、神の住まいとして建てた
のではない。民の祈りの家として建てたのである。
遍在性
神は宇宙を超越しながらも、なおかつ宇宙万物の中に遍在される。「遍在」とは、あまねく、どこにでも存在するという意味である。
「天にも地にも、わたしは満ちている」(エレ二三・二四)。
これは、神と宇宙自然との間に区別がなくなってしまうという意味ではない。神は宇宙自然との間に区別を持ちながら、なおかつ宇宙自然の中に内在される。神は超越者であり、同時に内在者である。キリストの使徒パウロはこう言っている。
「神は、私たちひとりひとりから遠く離れてはおられません。私たちは、神の中に生き、動き、また存在しているのです」(使徒一七・二七、二八)。
神は、単に遠くの天国におられるだけでなく、同時にすぐ近くにおられる。

「天にも地にも、わたしは満ちている」。
(3) 永遠にして不変
永遠性
神は、
「わたしは『わたしはある』という者である」(出エ三・一四)
と言われた。この原語のヘブル語を調べてみると、それは「わたしはあった」「わたしはある」「わたしはあり続ける」の、いずれの意味にもなるものである。神は永遠に存在される。
神には始まりがなく、終わりもない。死ぬこともなく、無に帰することもない。神は永遠の実在者であられる。
不変性
神のご本質とご性質は、永遠に変わることがない。
「主であるわたしは変わることがない」(マラ三・六)。
神の「あわれみ深く、情け深く、怒るのにおそく、恵みとまことに富む」(詩篇八六・一五)そのご性質は、永遠に変わることがない。神に関する真理は変化しない。
神は正しいかたであって、罰すべき者を必ず罰するが、赦すべき者は必ず赦される。このご性質も、永遠に変わることがない。
しかし、ご性質は変わることがないが、神の"ご意向"は変わることがある。
聖書には、神がニネベ(アッシリヤ帝国の首都)の人々の悪をご覧になってその町を滅ぼそうとしておられた、という記事がある。しかし人々が回心したので、「彼らに下すと言っておられたわざわいを思い直し、そうされなかった」(ヨナ三・一〇)。
この場合、神はご意向を変化されたことになる。しかし、神のご性質は変化していない。つまり「あわれみ深く、怒るのにおそい」神のご性質は変化していない。罰すべき者を罰するが、赦すべき者は赦すという神のご性質は、変化していないのである。
このように、神のご性質は変わらないが、神のご意向は人間の態度如何で変化することがある。ニネベの場合も、そこの人々の神に対する態度が変化したので、それに合わせて彼らに対する神のご意向も変化したのである。
(4) 自存者にして創造者
自存者
神は、他の何物にも依存することなく、自ら存在する自存者であられる。
人間が生きるには、空気や、水、食物、そのほか多くのものが必要である。それらがなければ人間は死んでしまう。
人間はそうしたものに依存した存在なのである。しかし神は、他の何物にも依存しておられない。存在の根拠を、ご自身の内に持っておられる。
神を造った者はいない。人間は偽りの神々を作ってきたが、真の神は誰にも造られない。神は自ら存在する、自存的な実在者なのである。
創造者
「はじめに神が天と地とを創造した」(創世一・一)。
神は創造者であられる。一方、造られた「天と地」、宇宙自然を「被造物」という。
創造者である神と、被造物である宇宙自然との間には、はっきりとした区別がある。"宇宙イコール神"とみる考え方(汎神論)は、聖書の教えるものではない。
神は無から宇宙万物を創造された。神は「無から有を呼び出される」(ロマ四・一七口語訳)かたである。
人は、"有から有を"生じさせることができるだけである。人が木を加工して机をつくる――これは有から有を造ったのである。
「無から有を呼び出す」という真の創造ができるのは、神だけである。
神は"造られない造るかた"なのである。
(5) 啓示者にして活動者
啓示者
神はまた、ご自身を啓示するかたであられる。神は今日、三つのものを通してご自身を啓示しておられる。
第一に、宇宙自然である。「神の永遠の力と神性」は、宇宙自然の中に啓示されている(ロマ一・二〇)。
第二に、聖書である。神はかつては、ご自身の預言者たちを通して啓示の御言葉を語られていたが、やがて預言者たちの言葉を一冊の『聖書』としてまとめるように導かれた。聖書は、神の啓示の御言葉である。
キリスト教会ではしばしば、聖書を「神の言葉」と呼ぶ。この意味は、聖書に記された思想・教え・真理が神からのものである、という意味である。ある人は、
「聖書は神の言葉だというが、聖書にはサタン(悪魔)の言葉も記されているではないか。たとえばサタンが、イエスの公生涯の初めに四〇日四〇夜荒野におられたとき、誘惑した際の言葉が記されている」
というかもしれない。しかし、それでも聖書は「神の言葉」なのである。つまり、神の言葉が「これはサタンの言葉だ」と言っているのである。
聖書が「神の言葉」だという意味は、聖書全体の思想・教え・真理が神からのものであり、啓示に基づくものである、ということなのである。
第三に、神はご自身をイエス・キリストを通して啓示しておられる。
「神は・・・・この終わりの時には、御子(キリスト)によって私たちに語られました。・・・・御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現われであり・・・・」(ヘブ一・二〜三)。
キリストは、「神の本質の完全な現われ」である。キリストにおいて、神の聖、義、愛、そのほか神のご本質、ご性質は、完全なかたちで啓示されている。

キリストは、神を完全なかたちで
啓示されたかたである。 プッサン画「エリコの盲人」
活動者
神はまた、活動し、ご自身の栄光を現わそうとされる。神は静的なかたではなく、むしろ動的なかたである。
「万軍の主の熱心がこれを成し遂げる」(イザ九・七)。
神は人間の救いのために、救いのご計画を進めてこられた。またご自身の栄光のために、人をご自身の民として選び、用い、また彼らを通してみわざをなされる。
「主はその御目をもって、あまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力をあらわしてくださるのです」(二歴代一六・九)。
なにもせず、ただ静かに座している神は、聖書の教える神ではなく、真の神でもない。
(6) 全知全能
神の全知全能とは、神の能力に関するものである。
全知性
まず全知とは、神がすべてを知っておられる、ということである。神は全歴史、全時間、全空間を一度に見渡すことができ、その出来事や事象のすべてを、つぶさに知っておられる。
人間の場合は、現在の事柄、それも自分の周囲にあるものを、見たり、聞いたり、触れたりして知るのみである。過去については言い伝えや文書記録等を通して知り、未来については想像を通して知るのみである。
しかし神は、過去・現在・未来を一度に見渡すことができる。そして、全時代、全世界、またすべての人の心にあることも、つぶさに知っておられる。
「造られたもので、神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています」(ヘブ四・一三)。
「あなたがたの頭の毛さえも、みな数えられている」(マタ一〇・三〇)。
神は全知であるので、未来のことも予知しておられる。「わたしは終わりの事を初めから告げ、まだなされていない事を昔から告げ・・・・」(イザ四六・一〇)。
このため、聖書には神からの予言(預言)の御言葉が数多くしるされている。
しかし私たちは、神の予知と、予定的意志とを混同してはならない。予知と予定とは別のものである。
神は、ご自身で予定しない事柄についても、予知しておられる。たとえばイスラエル民族が陥った悪の道は、神の予定によるものではない。しかし、神はそれを予知しておられた(申命三一・二〇)。
全能性
神が全能であるとは、ご自分が意志されたことを何でもすることができる、ということである。
「わたしは全能の神である」(創世一七・一)。
「神にとって不可能なことは一つもありません」(ルカ一・三七)。
ある人は、「神は全能で奇跡ができると言うなら、今それを見せてみよ」と言うかもしれない。
しかし全能とは、意志することをすべて行なうことができるという意味であって、もし意志がなければ、奇跡をむやみになさったりするわけではない。
また神の全能は、ご自身の他の性質に矛盾しない範囲でのみ発揮される。たとえば、「神が全能なら、自殺もできるか」と問う人もいるが、神には自殺ができない。なぜなら、これは先に述べた神の永遠性というご本質に反するからである。
神は「ご自身を否むことができない」(二テモ二・一三)。そのほか、悪を傍観することや、偽ること(ヘブ六・一八)、罪を犯すこと(ヤコ一・一三)もできない。これらは、ご自身の他の性質に反するからである。
神は、ご自身の他の性質に矛盾しない範囲でのみ全能を発揮し、ご自分の意志することを何でも行なうことができる。
神は天地宇宙を創造された。これは神の全能の力による。
神は幾つかの時代に、必要に応じて奇跡を起こされた。これは神の全能の力による。
また神は、ご自身の計画に基づいて、歴史の行方や、出来事の起きる時、場所等を予定することができる。これを「摂理」という。
キリストの降誕は、神の予定によるものであり、摂理に基づくものである。神はご自身の計画に基づき、歴史に上より介入され、出来事の成りゆきを導かれたのである。
この際、予知と予定の関係を誤解してはいけない。神は、予知して予定される。予定して予知ではない。クリスチャンは、第一ペテロ一・二で、
「父なる神の予知に従い・・・・選ばれた人々」
と呼ばれている。選ばれたから予知されたのではなく、予知に基づいて選ばれたのである。
先に予知があって、神はそれに基づいてご計画を立てられ、歴史の成りゆきや、ご自身の介入する出来事を予定される。これは神の全能の力によるのである。
(7) 霊であって人格的存在
霊性
「神は霊である」(ヨハ四・二四)。
神の存在様式は、物質ではなく、霊である。
イエスは「霊には肉や骨はない」(ルカ二四・三九)と言われた。神は、人間のような物質的身体を持っておられない。
実際、神がかつてイスラエルの人々にホレブ山(シナイ山)で現われたとき、人々は「何の姿も見なかった」。だからどんな偶像も造ってはならない、と彼らに命じられた(申命四・一五)。
神は、肉眼には見えないかたである。では、次のことはどう理解すべきだろうか。聖書にはしばしば、神の「顔」「手」「足」「目」「耳」といった表現が出てくる。
「わたし(神)の顔を見ることはできない」(出エ三三・二〇)。
「私(使徒ヨハネ)は、御座にすわっておられる方(神)の右の手に、巻き物があるのを見た」(黙示五・一)。
「(神の)御足の下には、サファイヤを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった」(出エ二四・一〇)。
そのほか、神の「目」(一列王八・二九)、「耳」(ネヘ一・六)などに関する表現もある。
こうした表現は、無限者である神を有限な人間が理解できるようにするための、単なる擬人的・象徴的表現ととる人々も多い。そのように考えることもできる。
しかし、聖書をよく調べていくと、そうした考えだけでは理解できないところも多い。
私たちは「霊」というと、空気や霧のように、ただ一様に広がる漠然としたものと考えやすい。しかし霊なる神は、肉眼には見えず無形であっても、霊の眼には「姿」あるかたなのである(民数一二・八)。
神は、無形の非物質だが、顔、手足、目や耳、その他に相当する各種の働きをする要因を持っておられる。それは物質的肢体や物質的感覚器官とは異なるが、有機的な働きをするそれぞれの霊的な各要因を持っておられるのである。
したがって、霊には霊的な姿がある。イスラエルの王であり預言者であったダビデは、神に向かって、
「私は・・・・御顔を仰ぎ見、目覚めるとき、あなたの御姿に満ち足りるでしょう」(詩篇一七・一五)
と祈った。また、かつてモーセが、神に「どうか、あなたの栄光を見せてください」と言ったとき、神は仰せられた。
「見よ。わたしのかたわらに一つの場所がある。あなたは岩の上に立て。わたしの栄光が通り過ぎるときには、わたしはあなたを岩の裂け目に入れ、わたしが通り過ぎるまで、この手であなたをおおっておこう。わたしが手をのけたら、あなたはわたしのうしろを見るであろうが、わたしの顔は決して見られない」(出エ三三・一八〜二三)。
神が、ご自身の「うしろ」「顔」等と言われる以上、神には霊的な御姿があるのである。
神の御姿は、私たちの想像をはるかに超えている。それを私たちの知性で把握することは難しい。
神は無限であって万物を超越し、肉の眼には見えず無形である。しかし、霊の眼に対しては、姿あるかたである。
人格性
神が霊であることはまた、神が生命であり、人格的存在であることを意味する(「人格」ではなく、本当は"神格"と言ったほうが良いのだろうが)。
哲学者は、しばしば感情のない非人格神を教えてきた。しかし、聖書に啓示された神は人格神である。
人格とは、知情意(知性・心情・意志)の働きをいう。また「わたし」という自意識や、自己決断力等をいう。神は語り、喜び、愛し、怒り、また悲しみ、あわれまれる。神は深い心情に富むかたである。
「(神は)あなたを喜ばれ、イスラエルの王座にあなたを着かせられた」(一列王一〇・九)。
神はまた、人間の堕落と罪に対して、慟哭とも言える心の痛みを示される。
「わたし(神)のはらわたは、彼のためにわななき、わたしは彼をあわれまずにはいられない」(エレ三一・二〇)。
イエス・キリストは、罪の中にあるエルサレムを見たとき、「ああ、エルサレム。エルサレム」と言って嘆かれた。
またラザロの墓の前に行ったとき、人間を支配する死の現実を見て「涙を流された」。主イエスのこの悲哀は、父なる神の悲哀でもある。
無感情の神は、聖書の教える神ではなく、また実在の神でもない。神は深い心の動きを持ったかたである。
(8) 聖
神は聖なる方である。神は聖書の中で、
「聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主」(イザ六・三)
と讃美されている。
神の聖に関して、三つのことを述べよう。第一に、「聖」とは単に道徳的に「きよい」という意味ではない。このヘブル原語の意味は、むしろ"分離"とか"超絶"といった意味を持っている。
神が「聖なる」かたであるというとき、それは基本的には、神が被造物の世界を超越し、離れておられるということを意味する。
その結果、汚れに染まったこの世界からも離れておられ、結局「きよい」という意味にもなるのである。
第二に、罪と汚れの中にある私たち人間が、聖なる神を見ることがあれば、人間は死ぬ。
「人はわたし(神)を見て、なお生きていることはできない」(出エ三三・二〇)。
とくに、人は神の御顔を見ることはできない、と言われている。
「あなたは、わたしの顔を見ることはできない」(同)。
私たちはたとえば、暗い中に長時間いたのち、太陽光のサンサンと降り注ぐ明るい戸外へ出ると、目がくらんでしまう経験をする。目が明るい光に耐えられないからである。
人が神を見ると死ぬというのは、これに少し似ている。人は神の御顔の聖なる光に耐えられないのである。
聖書には、「神を見た者はまだひとりもいない」(ヨハ一・一八)と言われている。人の罪汚れのゆえに、人が聖なる神を見ることは許されていない。見れば死ぬからである。
では、次のことはどう理解すべきだろうか。聖書には、人が神を見たと言われている箇所がある。
出エジプト記二四・一〇において、モーセとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老七〇人は、神の御前に出て行って「神を仰ぎ見た」、と記されている。
しかし、これは彼らが神の栄光の一部を見たということであって、神ご自身の御姿、とくに神の御顔を直接的に見たということではない。彼らは神ご自身の御姿の輪郭の一部を、おぼろげに見たに過ぎないのである。

モーセと長老たちは「神を仰ぎ見た」。しかし彼らは神の栄光の一部
を見たにすぎず、神の御姿、とくに神の御顔を見たのではない。
たとえば、ある人が王宮に行って、王座にすわる王の前に出たとしよう。彼は、王の前にひれ伏し、そのあと王を見ようとするが、恐れ多くて自分の顔を少ししか上げないために、王の足の部分をおおう服しか見なかった。
この場合、彼は王を見たことは見たが、実際は服しか見なかったのである。彼は王の姿を本当には見ていない。相手の顔を見なければ、本当に見たことにはならないのである。
モーセや長老たちは、神の御姿の栄光の一部を見た。しかし、御顔は見なかったのである。人は、聖なる神の御顔を見ることはできない。
第三に、神の聖に対して人間の内に引き起こされる感情は、畏怖である。
ある学者は、神の聖に対する人間の畏怖の感情を「ヌミノーゼ」という言葉で呼んでいるが、これは一般的な恐怖心のことではなく、自分をはるかに超えた偉大な存在に対して抱く「おそれかしこむ心」「おそれおおいと感じる心」である。
それは、荘厳な宇宙の大生命と峻厳な絶対的真理の前に自分がいるという、身震いするほどの感動の極致なのである。
通常の恐怖心――たとえば悪者に危害を加えられそうになるような時に抱く恐怖心は、一般に嫌悪感を伴う。
しかし、人が神の聖を感じて抱く畏怖の念は、嫌悪感を伴わない。むしろ、身震いするほどの喜びと神への愛に変わるのである。
神の「聖」は、神の大生命のまばゆい威光であり、その絶対的真理の峻厳さである。聖なる神を畏れることは、真理に近づく早道である。
「主をおそれることは、知識の初めである」(箴言一・七)
(9) 義
「義」とは、神が常に正しい態度を取られる、ということである。
聖書で使われている「義」の原語は、「まっすぐな」という意味である。神が「義」であるとは、神が人に対する関係の中で「まっすぐな」関係を持たれる――正しい態度を取られる、ということである。「義」は関係概念である。
神の義についても、三つのことを述べよう。第一に、神の義は罰すべき者を必ず罰する。
「主は・・・・罰すべき者は必ず罰して報いる者」(出エ三四・七)。
もし、犯罪の証拠がありながら逮捕しない警察官がいれば、それはもはや正しい警察官ではない。
またもし有罪の証拠がかためられていながら有罪にしない裁判官がいれば、それはもはや正しい裁判官ではない。同様に、もし神が罰すべき者を見ながら罰しないなら、彼はもはや正しい神ではない。
しかし、神は正しい方であるから、罰すべき者を必ず罰して報いられる。裁きは、神の義から来るのである。
第二に、神の義は、赦すべき者を必ず赦す。
「もし私たちが自分の罪を(神の前で)言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめて下さいます」(一ヨハ一・九)。
ここで、「神は愛であるから」とか「神が恵み深い方であるから」ではなく、「神は真実で正しい方」だから「罪を赦す」と言われていることに、注意しなければならない。神は義であるゆえに、赦すべき者を必ず赦される。
多くの人は、神の義はただ"こわいもの"と思っている。それをすぐ裁きに結びつけて考えるからである。しかし、裁きだけでなく、救いも神の義から来るのである。
悔い改めている人を神が赦すところに、神の正しさがある。神は正しい方であるから、悔い改めた人を赦される。
私たちの罪を神が赦してくださるのは、基本的に神が正しい方だから――神が義なる方だからである。神は「義」であるゆえに人を罰し、また「義」であるゆえに人を赦されるのである。

ソロモン王の裁判。神はソロモン以上に正しく、
知恵ある裁きをされる。 プッサン画
だから人の救いは、神の義なしにはあり得ない。神は義であるゆえに、人々のために救いの道を開かれた。そしてその「神の義は・・・・福音の中に啓示されている」(ロマ一・一七)。
第三に、神はご自身に対しても義であられる。
「神は・・・・偽ることができません」(ヘブ六・一七)。
神は偽りを言うことができない。ご自身が語られたことを、あとで曲げることができない。神は、ご自身に対しても正しい態度をとられ、義であられる。
神は、真理以外のことを語ることができない。神は「真実なかた」(一ヨハ五・二〇)である。だから私たちは、聖書に啓示された神の御言葉と御教えを、どこまでも信頼することができる。
(10) 愛
最後に、神は愛に富んでおられる。
「神は愛だからです」(一ヨハ四・八)。
哲学者の神が冷たく無関心な神であるのに対し、本当の神は、人間に対して強い関心を寄せ、深い愛情を持っておられる。
神が世界を創造し、そこに人間を置かれたのは、人間をご自身の愛の対象とするためであった。神が人間に自由意志をお与えになったのは、愛の対象は心の自由を持たなければならないからである。
神が御子イエス・キリストを世に遣わされ、また彼を十字架の死に渡されたのは、罪と滅びの中にある人間を愛し、彼らを救うためであった。
「(神は)あなたがたに対して忍耐深くあられるのであって、ひとりでも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを、望んでおられるのです」(二ペテ三・九)。
神の義が非常に父性的なものであるのに対し、神の愛は、非常に母性的である。
「母が子を慰めるように、わたし(神)もあなたがたを慰める」(イザ六六・一三)。
「女がその乳飲み子を忘れて、その腹の子をあわれまないようなことがあろうか。たとい彼らが忘れるようなことがあっても、わたしはあなたを忘れることはない。見よ、わたしは、たなごころ(手のひら)にあなたを彫り刻んだ」(イザ四九・一五)。
そのほか、聖書にはしばしば神の愛に関して、母性的な表現が使われている(マタ二三・三七、申命一・三一)。
神はふつう「天の父」と呼ばれ、父性的な方と表現されることが多いが、愛においては、あるときは非常に母性的なのである。

「母が子を慰めるように、
わたし(神)もあなたがたを慰める」
(イザ66:13) ラファエロ画「小椅子の聖母」
神の愛は、ご自身の前に正しく歩む者たちに対してだけでなく、罪の中にあって神に背き続ける人々に対しても向けられている。神は滅び行く人々に対して、深い悲哀を示さずにはいられない。
「わたしのはらわたは、彼のためにわななき、わたしは彼をあわれまずにはいられない」(エレ三一・二〇)。
神における"断腸の思い"である。これは、どんなに深い罪の中にある人々でも、「はらわた痛む」思いをもってその救われることを願う、慈母の心である。
真実の愛は痛みを伴う。罪人に対する神の愛は、慟哭にも似た叫びなのである。
神の愛は、ときに神の義と対立する。なぜなら、神の愛はすべての人が救われることを願う。しかし神の義は、罰すべき者を罰しなければならない。これは神の御心のうちで、激しい葛藤となり、心痛となってあらわれる。
しかし、この絶対矛盾的自己同一にこそ、実在の神の真実さがある。聖書は決して"常に冷静沈着な神"を教えない。実在の神は"心に痛みを持たれる神"である。私たちはこの神に対し、深い共感と崇敬の思いをおぼえざるを得ない。
義でない神はなく、愛でない神もない。真の神は、義であって愛であり、また愛であって義である。
仏教などでは、常に優しい慈愛だけの仏を説く。しかし、峻厳な義と、優しい愛の両方を持った存在者でなければ、実在の神とは言えない。
三 神の御名
神はご自身のお名前を、聖書の中に啓示された。神の御名は「ヤハウェ」(またはヤァウェ)である。
かつて中世から近代にかけてはエホバとも言われたが、これは学者の誤読によるものであって、ヤハウェが正しい。
ここでいう「名」とは、固有名詞である。固有名詞は「太郎」「花子」のように、その人個人の名前をいう。唯一の神にも固有のお名前があり、それをヤハウェという。
日本語の「神」、英語の“God”、ヘブル語のエロヒム(神)、ギリシャ語のセオス(神)等は、みな普通名詞である。しかしヤハウェは固有名詞であって、神の御名なのである。
たとえば新改訳(日本聖書刊行会)の旧約聖書を見ると、ところどころ「主」という文字が太文字で記されている。これは旧約聖書原文のヘブル語で、神の御名を表す神聖四字( )が記されているところである。 )が記されているところである。
ヘブル語は右から左へ読む。この四字は、ローマ字のYHWHに相当する子音である(ヘブル語では子音だけを記す)。
これをヤハウェ(ヤァウェ)と読むべきことは、幾つかの古代資料――たとえばキュロスのテオドレトスの記すサマリヤ人の読み方ヤーベ(ιαβε)や、アレクサンドリアのクレメンスによる読み方ヤーウエイ(ιαουαι)等によっても知ることができる。
神の御名YHWH(ヤハウェ)は、出エジプト記三・一四における神の御言葉、
「わたしは『わたしはある』という者である」
の「わたしはある」(エヘイェ)に由来するものと考えられている。「ヤハウェ」は、「彼はある」を意味する名であろう。
私たちはヤハウェの神聖な御名を、「みだりに唱えてはならない」(出エ二〇・七)。しかし、崇敬の心を持って発音することはよい。それは私たちの信仰告白の一部なのである。
「みだりに唱えること」を恐れるあまり、神の御名を全く発音しないのは、決して良いことではない。ユダヤ人は紀元前三世紀以降、全く発音しなくなってしまったようだが、それ以前はヤハウェの御名は、信仰の告白として日常的に発音されていた。
たとえばモーセは、説教の中で頻繁にヤハウェの御名を発音した(申命一八・一三ほか)。その説教を聞いたとき、民は、
「ヤハウェの仰せられたことは、みな行ないます」(出エ二四・三)
と答えた。ヤハウェの御名はまた、庶民同士の挨拶の言葉の中でも使われていた。ルツ記二・四には、ボアズが刈り入れ人たちに、
「ヤハウェがあなたがたと共におられますように」
と言い、それに答えて刈り入れ人たちが、
「ヤハウェがあなたを祝福されますように」
と言った箇所がある。人々は、挨拶の中でも、日常的にヤハウェの御名を発音したのである。
またヤハウェの御名には、短縮形があり、ヤハ(ヤァ)である。たとえば「ハレルヤ」は、ハレル・ヤハであり、"ヤハウェをほめよ"を意味する。
ヤハウェは、麗しい神の御名である。聖書の詩篇の作者は、こううたった。
「ヤハウェという名をお持ちになるあなたのみ、全地をしろしめすいと高き者であることを、彼らに知らせてください」(詩篇八三・一八)。

昔イスラエルの人々は、挨拶の言葉の中でも
ヤハウェの御名を発音した。 創元社『聖書物語』より
久保有政著(レムナント1995年8月号より)
|

 神
神