シスター・ドーラ
傷病者への愛
生涯を傷病者の看護にささげ、「シスター・ドーラ」と愛称されたドロシー・ウィンドハム・パチソン(1832〜78年) は、イギリスのヨークシャの小さな村に生まれた。父は牧師であった。
少女時代は体が弱く、とりたてて勉強はしなかったが、頭がよく、また見るもの聞くものから何でも汲み取ろうとする性質だった。そのため姉たちに比べても、見劣りするようなことはなかった。
彼女は、14歳のとき大病にかかったが、その苦しみに耐えぬいた。病気の体験によって彼女は、人は光明の面を見つめて生きねばならぬことを知った。
ドーラは、病気がちな母を助けながら、よく家事に従事していた。しかし、その母もドーラが21歳のときに、亡くなってしまった。
父は、ドーラのことを「わが家の日光」とほめるのが常であったが、当のドーラとしては、このまま田舎にうずもれてしまうのも残念、と思い始めていた。
ことにクリミア戦争におけるナイチンゲールの活躍を伝え聞いては、看護婦の仕事にあこがれ始めていた。
ドーラはある日、看護婦になりたい、と父に願い出た。この希望については、父も前々から知ってはいたが、ドーラに格別の基礎教養を与えなかったことも考えて、父は許すとも、許さぬとも言いかねていた。
29歳のときドーラは、独身のまま父の家を出た。はじめは小学校の教師になったが、ここでも生来の特長を発揮して、児童が病気になると必ずその家に行って熱心に看病するので、人々の信頼が厚かった。
こうして3年が過ぎた。やがて彼女は、ついに田舎の小さな病院で、念願の看護婦に専念する日を迎えることができた。
彼女が最も長い期間にわたって勤めたのは、バーミンガムから11キロあまり離れた、ワルソールという小都市にある病院であった。
19世紀中頃のこの辺は、粗野な人が多かった。ある夜、ドーラは街を歩いていると、一人の青年から石を投げつけられ、ひたいにケガを負った。
ところが、しばらくしてその青年が、炭鉱で負傷し、この病院に入院してきた。ドーラは一目見て、あの夜に石を投げつけた青年であるとわかった。けれども、そんなことはかりそめにも現さず、親切に看護をしてあげた。
だんだんケガもよくなってきた頃、青年は涙ぐんだ目で、ドーラにこう告白した。
「以前、石を投げつけて、あなたをひどい目にあわせた男があったはずです。その時の悪いヤツは私です。どうかゆるして下さい」。
彼女は静かに微笑んで、
「ええ、知っていますよ。あなたが入院なさった時からわかっていましたの」
と答えた。わかっていても、なおかつこんなに親切に手当てをしてくれたドーラの心に、青年は今さらのように、恥じ入るのだった。
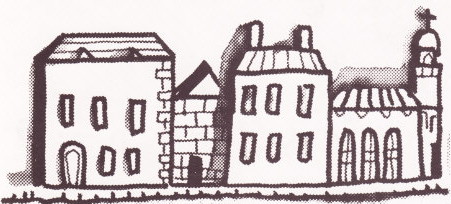
ドーラはある夜、ワルソールの街を歩いていると、
一人の青年から石を投げつけられた。
またある時、機械に腕をはさまれて大ケガをした若者が、病院に運びこまれてきた。医師はただちに診察をして、腕を切りとらねばならない、と患者に伝えた。
若者は泣きながら、
「どうか私の腕を助けてください」
と、かたわらにいたドーラに取りすがった。医者は、切断しないと命にかかわる、と決意をうながした。
そのときドーラが、思いきったように医師に言った。
「この腕を、私にお預け願えないでしょうか」
「バカな。すぐ切断のしたくにかからないと。
でないと、一命にかかわる恐れがある」。
ドーラは、今度は若者に言った。
「あなた、この腕は私に手当てさせて下さいますか」。
「どうぞお願いします」。
2人の問答を聞いて、医師は言った。
「結果はわかっている。私は一切知りませんよ」
医師は、その場を離れて行ってしまった。全責任はドーラの双肩(そうけん)にかかった。
こうなっては、ドーラもあとへは引けない。ただ神に祈り、全力を尽くして治療に当たるほかなかった。
日夜、ドーラは祈り、治療の手を尽くした。3週間たち、ドーラは前の医師に頼んで、再び腕を診察してもらった。
医師の前で、包帯が解かれていく。医師は子細に見守っている。包帯が全部とられ、腕が現われた。医師は若者に言った。
「腕を曲げてごらん。伸ばしてごらん」。
今度はドーラに言った。
「ああ! あなたは彼の腕を救いました」。
若者は、以来、自分のその腕を「ドーラの腕」と呼んだ。
人々はこうしたドーラを見ていたので、やむなく手足を切断しなければならない患者も、ドーラさえそばについていてくれればと、それを条件にして手術を受ける人もいた。

ドーラは彼の腕の治癒のために、必死に祈り、看病した。
しかし、ドーラも自分の病気には勝てなかった。彼女はガンにおかされつつあったが、働ける間はそれを秘(ひ)して、患者のために働いた。
1879年のクリスマス・イブ、貧しい友へのクリスマス・プレゼントを手(て)ずから整えた彼女は、
「主が見えます。門は広く開かれています」
と言って召天した。
人々は涙ながらに遺骸を葬り、立派な肖像をワルソールの街に建てて、彼女の記念とした。
この肖像を見て、ある人が言った。
「ドーラが亡くなっても、彼女のことは、だれ一人忘れ去る者はあるまい。それなのにどうして、魂のない肖像を建てねばならないのかね」。
すると一人の労働者が、それに答えて、誇らしげにこう述べた。
「私たちはもちろん、彼女を忘れるものではありません。けれどもね、ここに肖像が建っていると、知らない人が当地に来た時、あれは誰の像ですか、と尋ねるでしょう。その時には、こう答えてやるんですよ。あれは、私どものシスター・ドーラですと」。
〔聖書の言葉〕
「愛は、いつまでも絶えることがない」(コリ13:8)
久保有政著
|

 その他
その他